オーナー経営者にとって、自身の万が一に備えることは、事業の継続性と同じく重要な責務です。その備えの一つに、ご遺族の生活を支えるための「死亡退職金」があります。しかし、この死亡退職金の受取人を誰にするかという問題は、多くの経営者が見過ごしがちな、複雑な法的論点を内包しています。
会社の退職金規程において、受取人を単に「遺族」と定めているだけでは、残された家族の間に予期せぬ意見の相違を生む可能性があります。この記事では、死亡退職金が持つ異なる法的性質、すなわち税法上の扱いと民法上の扱いの違いを解説し、受取人の指定がいかに重要であるかを考察します。これは財産に関する取り決めであると同時に、人間関係という重要な資産を維持するための知見でもあります。
死亡退職金の異なる法的性質:相続税法と民法の視点
死亡退職金をめぐる問題が複雑化する根源は、その法的な位置づけが、準拠する法律によって異なる点にあります。具体的には、「相続税法」と「民法」が、それぞれ異なる定義を与えているのです。この構造的な相違を理解することが、問題解決の第一歩となります。
相続税法における「みなし相続財産」としての扱い
まず、相続税法上、死亡退職金は「みなし相続財産」として扱われます。これは、故人が亡くなったことを原因として遺族が受け取る財産であるため、実質的に相続によって得た財産と同様と見なして課税対象にする、という考え方です。生命保険金が同じく「みなし相続財産」とされることからも、その性質が理解できるでしょう。
ただし、この制度には遺族の生活保障という側面も考慮されており、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税限度額が設けられています。この非課税枠の存在は、死亡退職金が遺族にとって重要な生活資金となり得ることを国が認識している証左とも言えます。
民法における「受取人固有の財産」としての扱い
一方で、民法上、死亡退職金は原則として「相続財産」には含まれません。会社の退職金規程などに基づいて支払われるこの金銭は、遺産分割の対象となる故人の財産ではなく、指定された「受取人」が直接受け取る「固有の財産」と解釈されるのが一般的です。
この点が極めて重要です。民法上、相続財産ではないということは、たとえ他の相続人から「遺産として公平に分けるべきだ」と主張された場合でも、原則として遺産分割協議の対象とする必要がないことを意味します。税金の計算上は相続財産として扱われるにもかかわらず、遺産分割の対象にはならない。この法的な非対称性が、意見の相違が生じる要因となり得るのです。
受取人指定が不明確な場合に想定される問題
退職金規程における死亡退職金の受取人指定が明確でない場合、この法的な非対称性が顕在化し、ご遺族間の論点となる可能性があります。ここでは、具体的な二つのケースを見ていきましょう。
ケース1:「遺族」という包括的な指定がもたらす解釈の問題
典型的な例として、退職金規程で受取人を「遺族」とだけ定めているケースが挙げられます。この場合、「遺族」とは具体的に誰を指すのか、という解釈の問題が生じます。民法上の法定相続人の順位が適用されると考えるかもしれませんが、裁判例などでは、所得税法施行令に定められた順位(配偶者、子、父母、孫などの順)を参考に判断される傾向があります。
例えば、法定相続人として配偶者と二人の子がいる場合、仮に所得税法の順位に従って配偶者一人が全額を受け取ったとします。この配偶者は、民法上はその金銭を固有の財産として主張できます。しかし、子の立場から見れば、相続財産であれば得られたはずの取り分がない状況となり、不公平感を抱くかもしれません。金銭的な意見の相違は、感情的なものへと発展し、家族関係に影響を与えかねません。
ケース2:法定相続人以外への配慮と規程の重要性
昨今では、多様な家族の形が存在します。例えば、長年連れ添った内縁の妻や事実婚のパートナーに、感謝の意を込めて死亡退職金を遺したいと考える経営者もいるでしょう。しかし、これらのパートナーは民法上の法定相続人ではありません。
もし規程に「遺族」としか記載がなければ、彼らが死亡退職金を受け取ることは極めて困難になります。経営者本人の意思に反して、法律上の相続人に支払われてしまう可能性が高いのです。自身の死後、本当に財産を渡したい人物に確実に届けるためには、その人物を「受取人」として明確に指定しておく必要があります。
相続に関する問題を未然に防ぐための退職金規程の設計
では、不要な問題を未然に防ぎ、経営者の意思を確実に実現するためには、具体的にどのようにすればよいのでしょうか。その鍵は、退職金規程の計画的な設計にあります。
受取人を個人名で明確に指定する
一つの確実な方法は、死亡退職金の受取人を「配偶者 〇〇 △△」のように、個人名で明確に指定することです。これにより、その死亡退職金は民法上、指定された個人の「固有の財産」であることが明確になります。その結果、遺産分割協議の対象から切り離すことが期待でき、他の相続人との間で解釈をめぐる問題が生じる可能性を低減させます。
受取人の順位を定めて不測の事態に備える
より確実を期すのであれば、受取人の順位を定めておくことも有効です。例えば、「第一順位 配偶者 〇〇 △△、第二順位 長男 〇〇 太郎」というように、複数の候補者を順位付けして記載します。これは、万が一、第一順位の受取人が経営者本人より先に亡くなっていた場合や、同時に亡くなった場合などの不測の事態に備えるためのリスク管理策です。
定期的な規程の見直しと専門家への相談
家族構成や人間関係は、時と共に変化する可能性があります。一度定めた規程も、定期的に見直すことが不可欠です。子の独立、離婚や再婚、あるいは家族との関係性の変化など、ライフステージの節目ごとに、規程の内容が現在の自分の意思と合致しているかを確認することが重要になります。
また、退職金の規程作成や見直しにあたっては、税務と法務の両面に精通した税理士や弁護士などの専門家に相談することも有効な選択肢です。自社の状況や経営者の想いを正確に反映した、最適な規程を作成するための助言を得ることが期待できます。
まとめ
死亡退職金は、相続税法上の「みなし相続財産」と、民法上の「受取人固有の財産」という、異なる法的側面を持つ資産です。この構造を理解しないまま、退職金規程の受取人指定を不明確にしておくと、残されたご家族の間で意見の相違を生む一因となる可能性があります。
この問題を回避するための有効な策は、規程において、死亡退職金の受取人を氏名で明確に指定し、必要に応じて順位を定めておくことです。これは、単なる事務手続きではありません。残された家族への最後の配慮であり、経営者として果たし得る責務の一つです。
当メディア『人生とポートフォリオ』では、人生を構成する資産として、金融資産だけでなく、時間や健康、そして人間関係を重視する考え方を提示しています。死亡退職金をめぐる問題は、まさしく金融資産の扱い方が、人間関係という重要な資産の在り方に影響を与える一例です。ご自身の意思を明確な形で遺すことは、未来の不要な問題を避け、大切な人々の平穏な関係性を維持するための、重要な資産管理の一つと言えるでしょう。
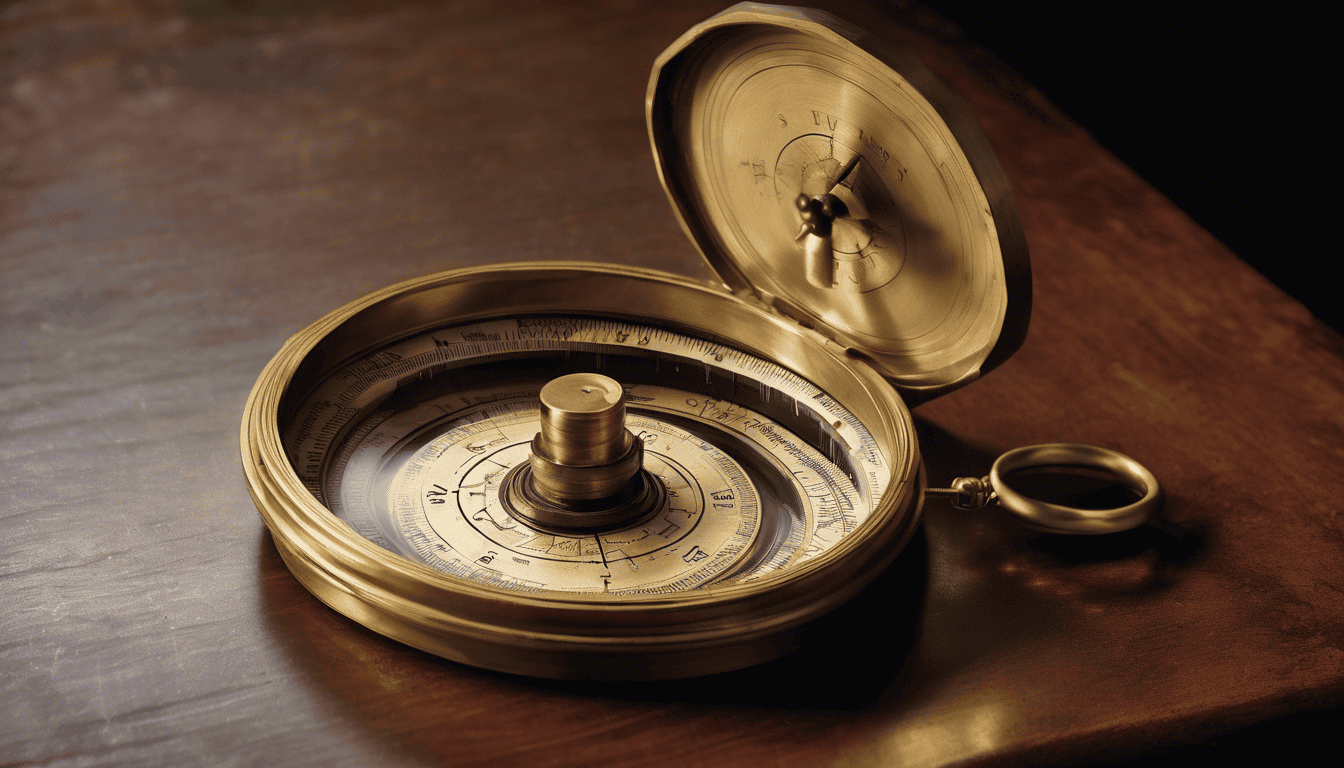










コメント