インターネット上に公開された情報が、半永久的に残り続ける現象、いわゆる「デジタルタトゥー」が社会的な課題となっています。過去の言動が検索結果を通じて容易にアクセス可能となり、個人の現在、そして未来の活動に制約を与えるケースは少なくありません。この状況は、多くの人にとって無視できない困難をもたらしています。
本稿では、一つの思考実験として、もしデジタル空間に残された過去の情報を消去する「忘れる権利」の行使に、税金が課される社会を想定します。この「忘却への課税」という仮説を通じて、個人の尊厳と社会のあり方を考察します。これは技術的な問題に留まらず、私たちがどのような社会構造を目指すべきかという、社会学的な問いかけでもあります。
デジタル社会がもたらす「消せない過去」という課題
かつての社会では、個人の過去の情報は、時間の経過とともにコミュニティの記憶から薄れ、自然に散逸していくのが一般的でした。しかし、デジタル技術とインターネットの普及は、この自然な忘却のプロセスを実質的に停止させました。検索エンジンは過去の情報を瞬時に再現し、ソーシャルメディアは過去の言動を永続的に記録します。
この「消せない過去」は、個人の人生に具体的な影響を及ぼします。例えば、就職活動において、採用候補者の過去の情報が判断材料とされたり、新たな人間関係の構築を妨げたりする事例が報告されています。問題の本質は、一度記録されたデジタルタトゥーが、その個人の現在の状況とは関係なく、評価の基準として機能し続ける点にあります。
人は時間と共に変化し、成長する存在です。しかし、デジタル社会は、特定の過去の時点をもって個人を固定化し、社会的な再起の機会を構造的に奪う可能性を内包しています。この課題は、個人の努力のみで対処することが困難であり、社会全体で向き合うべきテーマと言えます。
「忘れる権利」の概要とEUのGDPRにおける位置づけ
こうしたデジタル時代の課題に対し、一つの方向性を示したのが、EUの「GDPR(一般データ保護規則)」に盛り込まれた「忘れられる権利」です。これは、個人が自己に関するデータの削除を、データを管理する事業者に要求できる権利を指します。
この権利は、あらゆる情報を無条件に消去できるものではなく、表現の自由や公共の利益といった他の権利とのバランスを考慮した上で適用されます。その根底には、個人データは個人自身がコントロールすべきであり、過去の情報に過度に束縛されることなく、人生を再設計する機会は保障されるべきだという思想が存在します。
「忘れる権利」は、個人の尊厳を守るため、デジタル社会に適応した新しい権利のあり方を示したものと評価できます。これは、個人の人生を一つのポートフォリオと捉え、過去の負債を整理し、未来への投資に資産を再配分するという考え方とも通底します。つまり、法的な側面から、過去を整理し未来へ移行するための基盤となり得るのです。
思考実験:「忘れる権利」の行使に課税される社会
ここで、本稿の中心的な問いである、「忘れる権利」の行使に国家が税金を課す社会、いわゆる「忘却税」が導入された場合について考察します。この制度は、一見すると権利の乱用を防ぎ、運用上の公平性を担保するように見えるかもしれません。しかし、その先には、深刻な社会的格差や機能不全を招く可能性があります。
経済格差が「再起の権利」の格差に直結する
最も明白な影響は、経済的な格差が、人生をやり直す機会そのものの格差へと直接的につながることです。経済的に裕福な層は、税金を支払うことで過去のデジタル上の記録を合法的に消去し、社会的な評価を維持することが可能になります。彼らにとって、税金は過去を清算するための費用の一つに過ぎません。
一方で、経済的に余裕のない層は、税金を支払うことができず、過去のデジタルタトゥーを背負い続けることになります。その結果、雇用や社会参加など、人生における重要な機会を逸し続ける可能性があります。これは、単なる経済格差の問題ではなく、人生の再挑戦という、より根源的な機会の不平等を社会が制度的に生み出すことを意味します。
「忘却」が市場原理に組み込まれる可能性
税金という形で「忘れる」という行為に公的な価格が設定されると、それは市場原理に組み込まれていくことが予想されます。過去の情報を消去する行為が、一種のサービスとして産業化する可能性です。
高額な税金に加え、専門的な手続きを代行するコンサルティングサービスなどが生まれ、その費用も高騰していくかもしれません。結果として、「忘却」は一部の層のみが享受できるサービスとなり、人の「過去」そのものが取引対象となるような、倫理的な課題を内包する状況が生まれることも考えられます。
挑戦の萎縮と不寛容な社会構造
個人が失敗から立ち直りにくい社会は、必然的に人々が挑戦を避ける傾向を強めます。特に若者は、将来のリスクを恐れて発言や行動を萎縮させ、結果として新しいアイデアや文化の創造が阻害されるかもしれません。
さらに、過去の情報を消去できない人々に対する社会的な負の評価(スティグマ)は強化され、社会の分断を深める要因となる可能性があります。失敗した個人を許容せず、過去を理由に社会から排除するような不寛容な風潮は、社会全体の活力を削ぎ、停滞をもたらすことが懸念されます。
税金の役割から考える「忘れる権利」の公共性
ここで、税金という社会制度の本質に立ち返って考えてみましょう。税金とは、単なる資金徴収システムではありません。それは、私たちが暮らす社会が、何を価値あるものと見なし、何を公共財として支えるかを決定する、意思表示のメカニズムです。
「忘れる権利」の行使に税金を課すという制度は、「過去からの解放は、個人の責任と財力で獲得すべき私的なサービスである」という価値観を、社会が公式に肯定することを意味します。これは、失敗からの再起を個人の問題として捉え、社会的連帯よりも自己責任を重視する価値観の反映と言えるでしょう。
私たちは、税金の使途をむしろ逆の方向で考えるべきではないでしょうか。すなわち、税金は、誰もが失敗から立ち直り、再び社会に参加できるためのセーフティネットを構築するためにこそ使われるべきです。それは、教育や医療といった既存の公共サービスに加え、デジタル時代の新たなインフラとして「忘れる権利」を社会的に保障するといった領域に向けられることが望ましいと考えられます。
まとめ
本稿では、「忘れる権利」への課税という思考実験を通じて、その先に現れる社会の様相を考察しました。結論として、私たちは「忘れる権利」に税金を払うべきではありません。その理由は、以下の二点に集約されます。
第一に、「忘れる権利」は、経済力によって行使の機会が左右されるべきではない、個人の尊厳に関わる基本的な権利であるためです。
第二に、誰もが再挑戦できる可能性を社会的に保障することは、社会全体の寛容性と活力を維持するために不可欠な公共的な投資であるためです。
デジタルタトゥーの問題は、技術の進歩が生んだ新しい社会課題です。しかし、その対処法を考えることは、私たちがどのような社会を築きたいのかという、普遍的な問いに向き合うことに他なりません。誰もが過去の情報に過度に囚われることなく、人生というポートフォリオを健全に再構築できる社会。その実現に向けて、「忘れる権利」をどのように位置づけるか、社会全体で建設的な議論を深めていく必要があります。
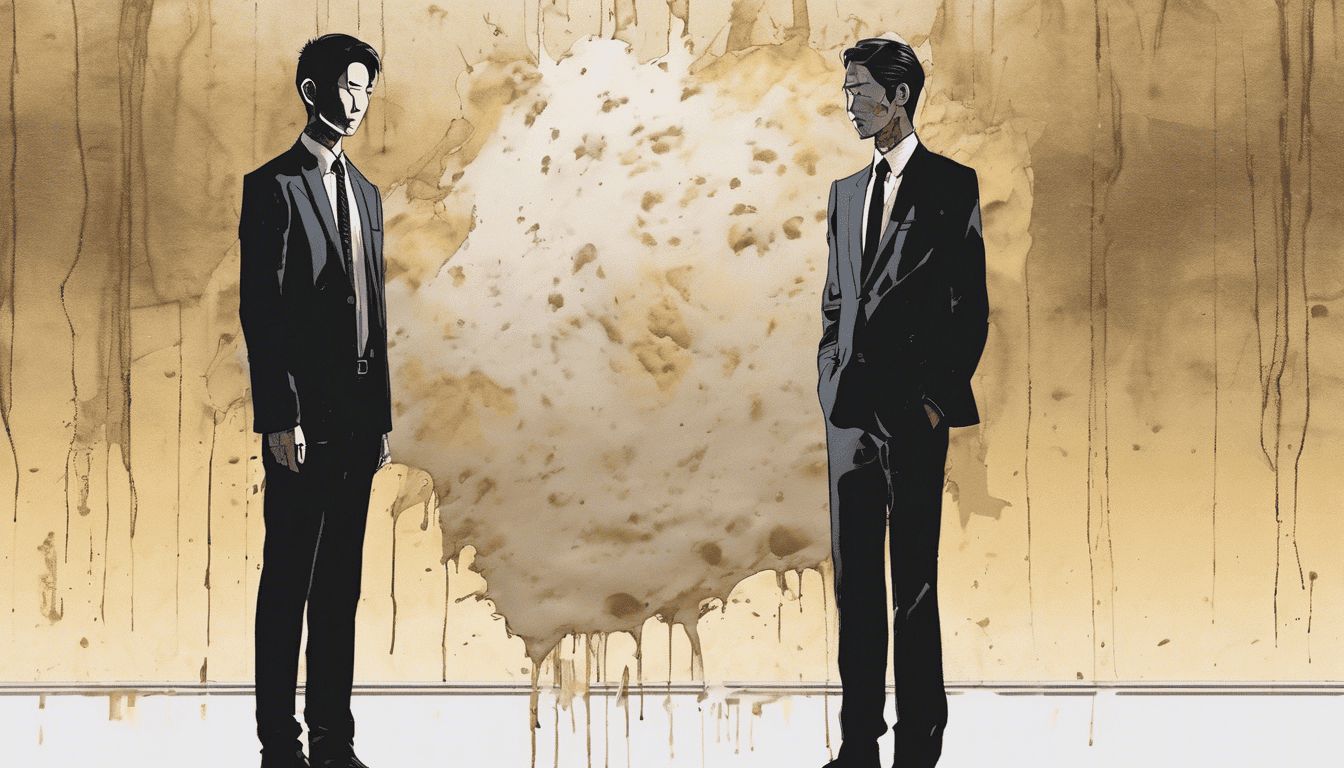










コメント