組織を率いるリーダーや、社会的に大きな影響力を持つ人物が、時に合理的とは言えない、あるいは他者への配慮を欠いた判断を下すことがあります。「あの温厚だった人が、役職に就いてから変わってしまった」という声は、多くの組織で聞かれる話です。私たちはこれを個人の性格の問題として捉えがちですが、近年の研究は、この変化が脳内で生じる物理的、化学的な作用に起因する可能性を示しています。
当メディア『人生とポートフォリオ』では、ピラーコンテンツである『脳内物質』を軸に、人間性の根源を探求しています。本記事ではその一環として、「権力」という社会的な要因が、私たちの脳機能にどのような影響を及ぼすのかを神経科学の観点から解き明かします。これは特定の個人を批判する目的ではなく、権力というシステムが内包する構造的な課題を理解し、より健全なリーダーシップと組織のあり方を考えるための考察です。
権力が引き起こす、脳内の化学的変化
権力を持つという経験は、私たちの脳内で特定の神経伝達物質の分泌バランスを変化させることが分かっています。この化学的な変化が、人の思考や行動に直接的な影響を与えます。
自信と決断力を高めるテストステロンの増加
社会的地位が高まると、男女を問わず、男性ホルモンの一種であるテストステロンの血中濃度が上昇する傾向が報告されています。テストステロンは、自信、競争心、リスクを取る意欲を高める作用があります。リーダーに求められる迅速な意思決定や、困難な状況に対応する行動力は、このホルモンの影響と無関係ではありません。
しかし、この作用には注意すべき側面もあります。テストステロンが過剰になると、他者への配慮が不足したり、自己中心的な傾向が強まったりする可能性があります。成功体験が重なることでテストステロンの分泌がさらに促進され、客観的なリスク評価能力が低下し、過大なリスクを許容しやすくなることも指摘されています。
報酬系を活性化させるドーパミンの影響
権力を行使し、自らの意思決定によって他者や環境をコントロールできるという感覚は、脳の報酬系を強く活性化させます。このとき、快感や意欲に関わる神経伝達物質であるドーパミンが放出されます。
このプロセスは、目標達成に向けたモチベーションの源泉となる一方で、その作用には依存症と共通する神経回路が関与していることも指摘されています。権力を行使すること自体が快感となり、その快感を得るために、より強い権力を求めるという行動につながる可能性があります。この状態は、本来の目的を見失わせ、権力の維持や拡大そのものが自己目的化してしまうという課題を内包しています。
共感性に関わる脳機能の変化
権力が脳に及ぼす特に注意すべき影響の一つが、共感性の低下です。他者の感情を理解し、その視点に立って物事を考える能力が、権力を持つことによって損なわれる可能性が、数多くの社会心理学や神経科学の研究で示唆されています。
ミラーニューロンシステムの活動低下
私たちの脳には、他者の行動を見ると、まるで自分がその行動をしているかのように活動する、ミラーニューロンシステムと呼ばれる神経回路が存在します。このシステムは、他者の意図を読み取ったり、感情に共感したりする上で重要な役割を担っています。
しかし研究によれば、権力を持つ立場に置かれた人は、このミラーニューロンシステムの活動が低下する傾向が見られます。これは、他者の表情や行動からその感情を察する脳の機能が、活動レベルで低下することを示唆します。結果として、他者の苦悩や困難に共感する能力が低下し、合理性や効率を優先するあまり、他者の感情に配慮しきれない判断を下すことへの心理的な抵抗が弱まる可能性があります。
共感性の低下が意思決定に与える影響
共感性の欠如は、サイコパシーと呼ばれる状態の特性の一つとして知られています。ここから、権力が人をそのような状態に近づけるという仮説が立てられることがありますが、権力を持つ人が臨床的な意味でサイコパシーと診断されるわけではありません。両者には明確な違いがあります。
しかし、機能的な側面から見ると、無視できない類似点も指摘されています。共感を司る脳領域、例えば眼窩前頭皮質などの活動が低下し、衝動的な行動を抑制する力が弱まるという点で、権力を持つ人が陥りやすい脳の状態と、サイコパシー傾向を持つ人の脳機能には共通項が見られます。権力という特殊な環境が、後天的、かつ一時的に、共感能力が著しく低い状態、いわば「機能的な共感性低下」とでも呼べる状態を脳内に生じさせる可能性があるのです。
権力の神経科学的影響と、組織が向き合うべき課題
権力が脳機能に及ぼす影響を理解することは、リーダーシップのあり方を根本から問い直すきっかけとなります。問題は権力そのものではなく、その神経科学的な影響を自覚し、適切に対処する仕組みを持たないことにあります。
リーダーに求められるメタ認知の重要性
最も重要な対策の一つは、リーダー自身がメタ認知の能力を高めることです。メタ認知とは、自分自身の思考や感情、行動を、第三者の視点から客観的に認識する能力を指します。「現在の自分の判断は、権力による脳の変化に影響されていないか」「他者の意見に真摯に耳を傾けられているか」と、常に自問自答する姿勢が求められます。
これは、個人の意志の力だけで達成できるものではありません。定期的に内省の時間を持つ、信頼できるメンターやコーチから客観的なフィードバックを得るなど、意識的に自分を客観視する習慣を日々の活動に組み込むことが有効です。
組織として導入を検討すべき仕組み
個人の努力だけに依存せず、権力の影響を緩和するためには、組織的な仕組みが極めて重要です。例えば、部下や同僚など、複数の立場からリーダーを評価する360度評価は、権力を持つ人が見失いがちな他者からの視点を提供する有効な手段となり得ます。
また、意思決定のプロセスに多様な意見を持つメンバーを意図的に参加させ、異論を歓迎する文化を醸成することも、権力行使の偏りを是正するための重要な仕組みです。権力者に心地よい情報だけが集まるエコーチェンバー現象を防ぎ、健全な批判精神を組織内に維持することが、リーダーと組織の双方を長期的に守ることにつながります。
まとめ
権力は、人の性格を単純に変えてしまうものではなく、テストステロンやドーパミンの分泌を促し、共感を司る脳領域の活動を低下させるという、明確な化学的変化を脳内にもたらします。この神経科学的な事実を理解することは、リーダーシップに伴う本質的な課題を直視することに他なりません。
自信や決断力といった肯定的な側面を活かしつつ、共感性の低下や衝動性の高まりといった注意すべき影響をいかに制御するか。その鍵は、リーダー個人のメタ認知と、それを支える組織的なフィードバックの仕組みにあります。
当メディアが提唱する「思考と健康と人間関係が幸福の土台である」という思想に照らし合わせれば、権力が脳に及ぼす影響は、まさにこの土台を揺るがしかねない重要な論点です。権力を持つ人も、そうでない人も、この神経科学的な知見を共有することで、より建設的で、人間性を尊重した関係性を築くことができるはずです。リーダーシップとは単に権力を行使する技術ではなく、その影響を深く理解し、自らを律する知性そのものであると言えるでしょう。
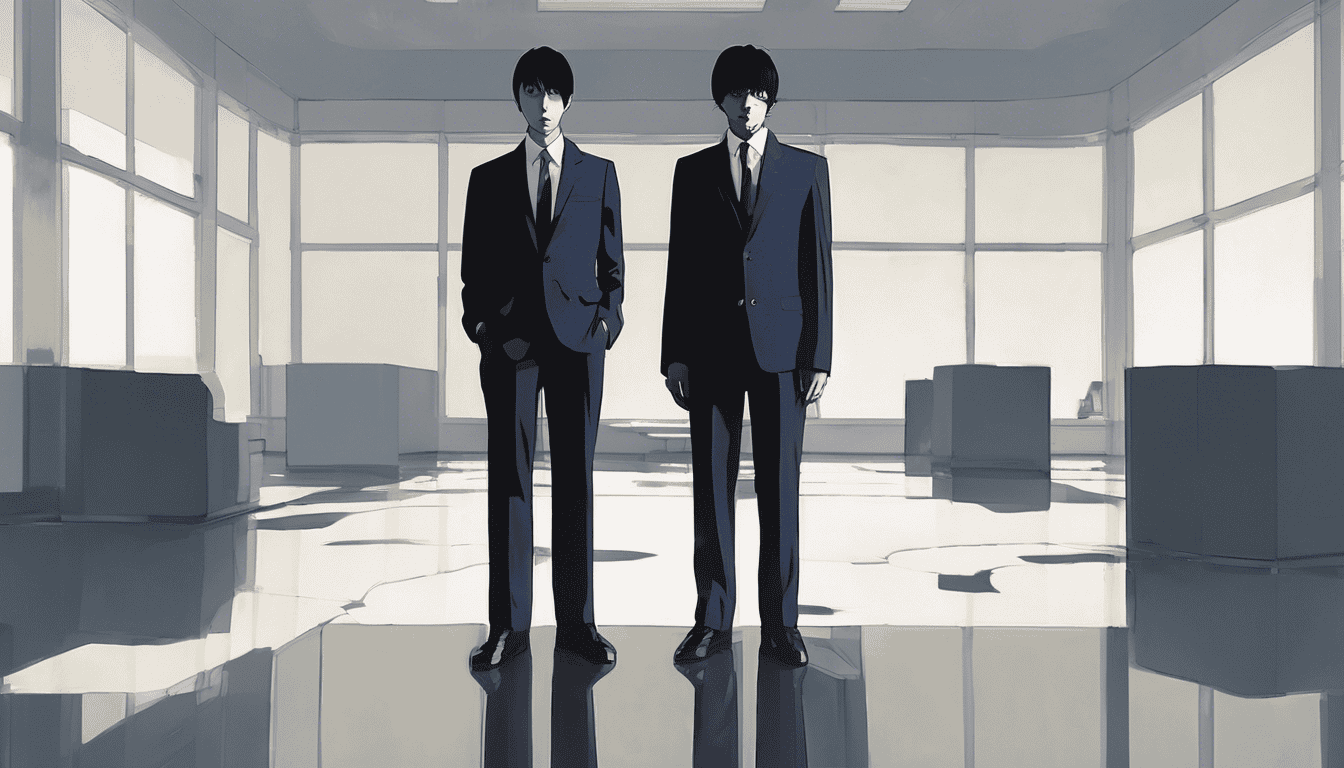










コメント