はじめに
深夜までオフィスに残る同僚、目的が曖昧な会議、そして成果よりもプロセスばかりが問われる評価。日本の組織で働く多くの人が、こうした非効率な慣習に一度は疑問を抱いたことがあるかもしれません。成果を出すことよりも、「いかに頑張っているか」をアピールすることが求められるような空気に、精神的な負担を感じている方も少なくないと考えられます。
この現象は、単なる個人の問題や、特定の企業の体質に留まるものではありません。当メディア『人生とポートフォリ』では、社会全体を一種の「ごっこ遊び」として捉える視点を探求しています。今回の記事は、その中でも『「魂」の不在』というテーマに属します。目的や本質が見失われ、形式だけが自己目的化していく社会の側面、すなわち「苦労しているふりごっこ」がなぜ蔓延するのか。その構造を社会学的な視点から考察します。
「頑張り」の可視化という同調圧力
なぜ、私たちは成果そのものよりも「頑張っている姿」を見せることにエネルギーを費やす傾向にあるのでしょうか。その根底には、成果が曖昧であったり、長期的な視点が必要であったりする業務において、評価者がプロセスに頼らざるを得ないという構造的な問題が存在します。
しかし、より本質的な要因として、日本社会に根強く存在する同調圧力が考えられます。組織という共同体において、個人の行動は常に他者から観察され、評価されています。その中で、「自分は組織に貢献している」「ルールに従っている」という姿勢を他者に分かりやすく示すための手段として、「頑張っているアピール」が機能している可能性があります。
つまり、長時間労働や非効率な作業への参加は、業務上の必要性からではなく、共同体への忠誠心を示すためのシグナルとして消費されているのかもしれません。これは、目に見える形で集団への帰属を証明し、異端であると見なされることを避けるための、無意識の防衛機制と捉えることもできます。
村落共同体としての日本組織
この「ごっこ遊び」が成立する文化的土壌として、日本の組織が持つ「村落共同体」的な性質を考慮に入れる必要があります。近代的な企業システムという外見を持ちながらも、その内部では、かつての農耕社会に由来する価値観や行動様式が色濃く残っている側面があります。
秩序維持のための「儀式」
村落共同体において重要な価値の一つは、個人の突出した成果よりも、共同体全体の和と秩序を維持することでした。そのためには、全員が同じルールに従い、同じように汗を流すという共通体験が重要視されていました。
現代の組織における非効率な会議や過剰な報告業務、そして長時間労働は、この共同体の秩序を維持するための「儀式」として機能している側面があります。その行為自体に合理的な意味は薄くとも、それに参加すること自体が、組織への帰属意識と忠誠心を表明する行為となります。この儀式に参加しない者は「和を乱す者」と見なされ、共同体からの心理的な排除を受けるリスクを伴う場合があります。
プロセス評価の功罪
もちろん、プロセスを評価すること自体が、常に問題なわけではありません。結果だけでは測れない粘り強さやチームへの貢献、試行錯誤の過程を評価することは、挑戦を促し、組織の学習能力を高める上で有効な場合もあります。
問題となるのは、その評価が形骸化し、本来の目的である「成果」から切り離された場合です。プロセスが自己目的化し、いかに苦労したか、いかに時間をかけたかという「苦労ごっこ」が評価の主軸になると、組織は本来の目的を見失います。これが、当メディアで探求する『「魂」の不在』という状態です。魂を失った儀式は、参加者の精神的なエネルギーを消耗させ、組織全体の生産性を徐々に低下させる要因となります。
なぜ私たちは「ごっこ遊び」に付き合ってしまうのか
この不合理な「ごっこ遊び」の構造を理解していても、そこから抜け出すことには困難が伴います。その背景には、個人の合理的な判断を抑制する、いくつかの心理的な要因が関係していると考えられます。
「逸脱」への恐怖
人間は社会的な生き物であり、所属する集団からの孤立を本能的に避ける傾向があります。たとえ非効率だと分かっていても、「みんなやっているから」という理由で、周囲の行動に合わせようとします。この「ごっこ遊び」から降りることは、共同体からの「逸脱」を意味し、「やる気がない」「協調性がない」といったネガティブなレッテルを貼られることへの強い心理的な抵抗感を伴います。その結果、多くの人は不満を感じながらも、安全な多数派に留まることを選択する傾向にあります。
評価システムの機能不全
個人の成果を客観的かつ公正に評価するシステムが組織内に確立されていない場合、個人はより分かりやすい評価指標に頼る傾向が強まります。それが、残業時間や休日の出勤といった「頑張りの可視化」です。成果で正当に評価されるという信頼がなければ、個人は最も手軽で低リスクな評価獲得手段である「頑張ってるアピール」に傾倒しやすくなります。この状況が、多くの誠実な働き手に過度な負担をかけ、主体的な行動を抑制する一因となっています。
「ごっこ遊び」から距離を置くための思考法
では、私たちはこの「魂」の不在な状況に、ただ消耗し続けるしかないのでしょうか。構造を理解することは、そこから自由になるための第一歩となります。ここでは、そのための具体的な思考法を提案します。
自分の「評価軸」を持つ
会社の評価軸だけを自分の価値基準の全てにしてしまうと、私たちは組織の「ごっこ遊び」に影響を受けやすくなります。重要なのは、会社とは別の、自分自身の評価軸を持つことです。
このメディアで提唱する「ポートフォリオ思考」は、まさにこのための考え方です。人生を構成するのは仕事だけではありません。時間、健康、人間関係、情熱といった多様な資産が存在します。無駄な頑張りに費やされる時間は、他の重要な資産を毀損するコストとして認識する必要があります。会社の評価という一面的なものさしから距離を置き、人生全体のポートフォリオを豊かにするという視点を持つことが、精神的な自立を促します。
「成果」による貢献を再定義する
「ごっこ遊び」から距離を置くことは、仕事への貢献を放棄することと同義ではありません。むしろ、より本質的な貢献を目指すことにつながります。長時間労働という「量」のアピールではなく、時間あたりの生産性を高めるという「質」で貢献する道を探ることです。
例えば、非効率な業務プロセスを具体的に改善する提案を行う、あるいは、短い時間で高い成果を出すことで、時間ではなく成果で評価される前例を自ら作る。これは、既存のルールへの単なる反発ではなく、組織全体をより良い方向へ導くための、高度な貢献と捉えることができます。対立ではなく、より高い視点から組織の課題に向き合う姿勢が求められます。
まとめ
日本の組織に蔓延する「苦労しているふりごっこ」は、個人の意識の問題というよりも、同調圧力や村落共同体的な文化といった、社会構造に根差した現象と考えられます。目的を見失い、形式だけが自己目的化したこの「魂」の不在な状況は、多くの人に精神的な負担を与えています。
しかし、この構造を客観的に理解することで、私たちはその不合理なゲームの渦中から一歩引いて、冷静に状況を観察することが可能になります。会社の評価軸だけに依存せず、自分自身の人生という大きな視点から物事を捉え直すこと。そして、「頑張ってるアピール」という儀式的な貢献ではなく、本質的な「成果」によって貢献する道を探ること。
この慣習の構造を理解することで、その状況に無自覚に従うのではなく、一歩引いて客観的に捉えることが可能になります。自分自身の価値基準に基づき、組織との健全な距離感を保ちながら、未来への道を模索していく一つの道筋が見えてくるのではないでしょうか。



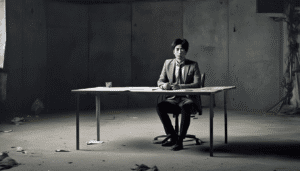
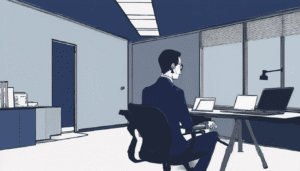






コメント