かつて、私たちの親や祖父母の世代には、社会全体が共有する明確な目標がありました。高度経済成長、国家の発展、あるいは特定のイデオロギーの実現。それらは、個人の人生に意味と方向性を与える、いわば「大きな物語」として機能していました。しかし現代において、私たちはその物語を失いました。この記事では、フランスの哲学者ジャン=フランソワ・リオタールが提唱した「大きな物語の終焉」という概念を解説し、その後に私たちが何を拠り所にするようになったのか、そしてこれからどのように生きるべきかを探求します。
これは、当メディア『人生とポートフォリオ』が掲げる『序論:社会という名の「ごっこ遊び」』というテーマ系譜に連なる考察です。社会というシステムの中で、満たされない感覚や本質的な目的の不在を感じる方にとって、現状を客観視し、次の一歩を考える上での指針となることを目指します。
「大きな物語の終焉」が意味するものとは
「大きな物語の終焉」とは、社会全体を統合し、人々の行動を方向づける普遍的な価値観や目標が失われた状態を指します。かつては、宗教、国家、科学の進歩といったものが、私たちの生きる意味を支える普遍的な指針を提供していました。この会社で働き、この国に貢献し、家族を築くこと。その一つひとつの行為が、より大きな目的の一部として意味づけられていたのです。
しかし、グローバル化、情報化、価値観の多様化が進むにつれて、そうした単一の物語はその説得力を失いました。唯一絶対と信じられていた「正解」はなくなり、私たちは明確な指針がない不確実な状況に置かれています。何を信じ、何を目標にすれば良いのかが分からない。このような、方向性を見失いがちな感覚こそ、「大きな物語の終焉」を生きる私たちが共通して抱える課題といえるでしょう。
空白を埋める「小さなごっこ遊び」への傾向
人間は、本質的な意味の空白状態を避けようとする傾向があります。失われた「大きな物語」の空白を埋めるため、私たちは無意識のうちに、より小規模で、より身近な物語を拠り所にするようになりました。これを、当メディアでは「小さなごっこ遊び」と呼んでいます。これは、本質的な価値や目的を見失ったまま、特定のルールや役割、形式だけを模倣し、そこに安心感を見出そうとする行為です。
組織という名の「ごっこ遊び」
その代表例が、会社や組織という閉じた世界への過度な没入です。本来、企業活動は社会に価値を提供するための一つの手段にすぎません。しかし、「大きな物語」を失った個人にとって、会社のビジョンや売上目標、キャリアパスといったものは、かつての物語の代替物として機能することがあります。
社内での評価や地位、特定の役職を演じること自体が目的化し、そのルールの内側で承認を求める「組織ごっこ」が始まります。そこでは、自分の人生全体における幸福よりも、組織内での相対的な立ち位置が優先されがちです。これは、人生全体に関わる本質的な問いから意識をそらし、限定的なルールの中で安住するための、一つの心理的な防衛機制と見ることもできます。
ライフスタイルという名の「ごっこ遊び」
もう一つの典型が、特定のライフスタイルを形式的に模倣する動きです。例えば、ミニマリズム、SDGsへの貢献、自己啓発といったものは、それ自体が価値ある概念です。しかし、その本質的な探求を欠いたまま、他者との差異化や自己肯定感を得るための道具として消費されるとき、それらもまた「ごっこ遊び」へと変質する可能性があります。
「これこそが正しい生き方だ」という新たな小さな物語を拠り所にすることで、かつての大きな物語が与えてくれたような所属感やアイデンティティを得ようとするのです。しかし、その根底にあるのは、自らの価値基準で選択するという主体性ではなく、外部から与えられた「正解」に準拠しようとする傾向である可能性が考えられます。
なぜ私たちは「ごっこ遊び」から抜け出しにくいのか
「大きな物語の終焉」という不確実な時代において、私たちが「ごっこ遊び」に惹かれるのは、ある意味で自然なことかもしれません。人間には、所属欲求や承認欲求があり、明確なルールやコミュニティの中に身を置くことで安心感を得ようとする心理的な傾向があります。
問題となり得るのは、その「ごっこ遊び」が、いつしか自分の人生そのものであるかのように認識されてしまうことです。組織のルールや特定のライフスタイルが、自分の価値の全てを規定するようになると、私たちはその小さな世界の評価に左右され、より広い世界に存在する可能性から自らを切り離してしまうことに繋がりかねません。
まとめ:自分自身の「人生の物語」を創造する
「大きな物語の終焉」という状況は、悲観的に捉える必要はなく、むしろ個人の主体性が尊重される時代の到来と捉えることができます。それは、国家や社会から与えられた既成の指針に従う時代が終わり、私たち一人ひとりが、自らの人生を主体的に設計していく時代が来た、ということを示唆しています。
「組織ごっこ」や「ライフスタイルごっこ」の限界を認識することは、そのための第一歩です。次の段階は、自分自身の価値基準に基づいた、本質的な物語を主体的に創造していくことです。
ここで重要になるのが、当メディアが提唱する「ポートフォリオ思考」です。人生を、仕事やお金(金融資産)だけでなく、時間、健康、人間関係、そして情熱といった複数の資産の集合体として捉え直す視点です。この俯瞰的な視点を持つことで、特定の「ごっこ遊び」への過度な依存から距離を置き、人生全体のバランスを最適化するという、より大きな目的を見出すことが可能になります。
あなたにとって本当に大切な時間は何か。何をしている時に、心からの充実感を得られるのか。誰との関係を育むことが、あなたの人生を豊かにするのか。これらの問いに向き合うプロセスこそが、あなただけの「人生の物語」を構築する作業そのものです。社会から与えられる既成の指針に頼るのではなく、自らが主体となって人生を設計していくことを、検討してみてはいかがでしょうか。



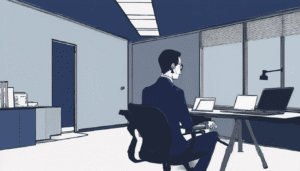







コメント