「ベーシックインカム」という言葉について、多くの人は政府が国民の生活を保障する、手厚い福祉国家を目指す左派的な政策という印象を持つかもしれません。
しかし、その構想の源流の一つが、市場原理を重視し「小さな政府」を掲げた経済学者、ミルトン・フリードマンによるものだったという事実は、この政策の多面的な性質を示唆しています。
本稿では、政治的なレッテルを離れ、フリードマンが提唱した「負の所得税」という提案について解説します。この一見すると矛盾した関係性は、現代社会が直面する課題を考える上で、重要な視点を提供します。
ミルトン・フリードマンとは
「負の所得税」を理解する前提として、提唱者であるミルトン・フリードマンの思想的背景を明確にする必要があります。
フリードマンは20世紀を代表する経済学者であり、政府の市場への介入を最小限に抑え、個人の自由な経済活動を最大限に尊重すべきだと主張しました。いわゆる「新自由主義」や「リバタリアニズム」の思想的支柱として知られ、英国のサッチャー政権や米国のレーガン政権の政策に大きな影響を与えた人物です。
彼の思想の核心は、「小さな政府」の実現にあります。規制緩和、民営化、そして自由貿易を推進し、国家の役割を国防や司法といった必要最低限の機能に限定することを目指しました。このような人物が、なぜ一見すると福祉政策のように見える制度を提唱したのでしょうか。その答えは、「負の所得税」の仕組みとその目的にあります。
「負の所得税」とは。フリードマンの提案
フリードマンが1962年の著書『資本主義と自由』で提唱した「負の所得税」は、所得税の仕組みを応用したもので、貧困問題に対処するための、シンプルかつ効率的な解決策として提示されました。
所得税の逆転:給付の仕組み
通常の所得税は、所得がある一定額を超えた場合に、その一部を国に納める制度です。これに対し、「負の所得税」は、所得が一定の水準(免税点)に満たない人々に対して、政府が不足分の一部を現金で給付する仕組みを指します。
具体的な例で説明します。仮に、免税点が100万円、給付率が50%に設定されたとします。
- 所得が0円の場合:免税点100万円との差額は100万円です。その50%である50万円が政府から給付されます。
- 所得が50万円の場合:免税点100万円との差額は50万円です。その50%である25万円が給付されます。この人の手元に残る金額は、自身の所得50万円と給付金25万円を合わせた75万円となります。
- 所得が100万円の場合:免税点と一致するため、納税も給付もありません。
- 所得が150万円の場合:免税点を超えているため、通常の所得税のルールに従って納税します。
この制度の特徴は、所得が増えるほど給付額が緩やかに減少していく点です。これにより、働く意欲への影響を抑えながら、最低限の所得を保障できるとフリードマンは考えました。
フリードマンの目的:官僚機構の効率化と個人の自由
フリードマンが「負の所得税」を提唱した目的は、単なる貧困救済に留まりませんでした。彼の意図は、より根本的なものでした。それは、肥大化し非効率化した社会保障制度と、それを運営する官僚機構を根本から見直すことでした。
当時の米国には、住宅手当、食料引換券、医療扶助など、多種多様で複雑な福祉プログラムが存在していました。フリードマンは、これらの制度が行政コストを増大させ、官僚の裁量権を生み、人々から自己決定の機会を奪っていると指摘しました。
彼の提案は、これら無数の現物支給や補助金をすべて廃止し、「負の所得税」という現金給付に一本化するというものです。これにより、以下の二つの効果が期待されました。
- 行政コストの削減:複雑な審査や給付手続きが不要になり、官僚機構を大幅に縮小できる可能性があります。
- 個人の選択の自由の尊重:政府が用途を限定するのではなく、個人が受け取った現金を何に使うかを自ら決定する。これは、市場における消費者の選択を尊重する、フリードマンの一貫した思想の表れです。
つまり、「負の所得税」は福祉政策の側面を持ちながらも、実質的には「小さな政府」を実現するための手段であったと解釈できます。
「負の所得税」とベーシックインカムの比較
フリードマンのこの提案は、現代で議論されるベーシックインカムの重要な源流と見なされています。両者には共通点もありますが、その根底にある思想には明確な違いが存在します。
共通点:福祉の簡素化と現金給付
両者に共通するのは、既存の複雑な社会保障制度を簡素化し、現金で直接給付するというアプローチです。手続きの煩雑さや行政の非効率性を解消し、人々が直接的な支援を受けられるようにするという点では、目的を共有しています。
相違点:思想的背景と対象範囲
決定的な違いは、その思想的背景と給付の対象範囲にあります。
- 負の所得税(フリードマン):
- 対象:低所得者に限定されます。所得に応じて給付額が変動する「選別主義」的な制度です。
- 思想:市場メカニズムへの信頼が根底にあります。既存の福祉制度を効率化し、政府の介入を最小化することが目的です。個人の労働意欲を維持することも重視されます。
- ベーシックインカム:
- 対象:所得や資産に関係なく、すべての国民に一律で無条件に給付されます。「普遍主義」的な制度です。
- 思想:その背景は多様ですが、多くの場合、人間の尊厳を支える生存権の保障や、AIの発展による雇用の変化といった未来への備えなど、より社会権的な発想に基づいています。
このように、フリードマンの「負の所得税」は右派的なリバタリアニズムから、現代のベーシックインカム論は左派的な人権思想から生まれてきた側面があり、同じ「現金給付」という手法を用いながら、目指す社会像は異なります。
なぜ今、フリードマンの思想が注目されるのか
発表から半世紀以上が経過したフリードマンの「負の所得税」が、なぜ今、再び注目を集めているのでしょうか。それは、この提案が現代社会の抱える複数の課題に対して、示唆に富む視点を提供しているからです。
第一に、硬直化した行政システムへの問題意識です。複雑で非効率な制度を維持するためのコストに対する疑問は、世界共通の課題です。よりシンプルで透明性の高い仕組みを求める声が、フリードマンの提案への再考につながっています。
第二に、政治的な分断を超える可能性です。「負の所得税」やベーシックインカムは、右派が重視する「小さな政府」「自己責任」と、左派が重視する「貧困削減」「格差是正」という、本来は相容れない価値観を接続する可能性を秘めています。左右のイデオロギー対立が行き詰まりを見せる中で、現実的な解決策として検討されています。
そして最後に、「個人の自律性」という現代的なテーマとの関連性です。フリードマンの提案は、国家による過剰な干渉(パターナリズム)を避け、個人が自らの判断で資源を配分することを尊重する思想です。これは、既存の社会システムの中で、個人が自身の価値基準で生きる道を模索する上での一つの参考になります。
まとめ
新自由主義の代表的な論者であるミルトン・フリードマンが提唱した「負の所得税」。それは、単なる福祉政策ではなく、肥大化した官僚機構を見直し、個人の自由を尊重することを目的とした、リバタリアニズムに基づく提案でした。
この歴史的な事実は、私たちに重要な示唆を与えます。ベーシックインカムというテーマが、単に「右か左か」という二元論では捉えきれない、奥深い思想的広がりを持っているということです。
社会的な課題に向き合うとき、私たちは無意識に「右派の政策」「左派のアイデア」といったレッテルを貼って思考を限定してしまうことがあります。しかし、フリードマンの例が示すように、物事の本質は、そうしたレッテルを一度離れ、その思想の根源にある「問い」そのものに目を向けたとき、見えてくるのかもしれません。この視点は、複雑な現代社会を理解する上で有益なものとなる可能性があります。
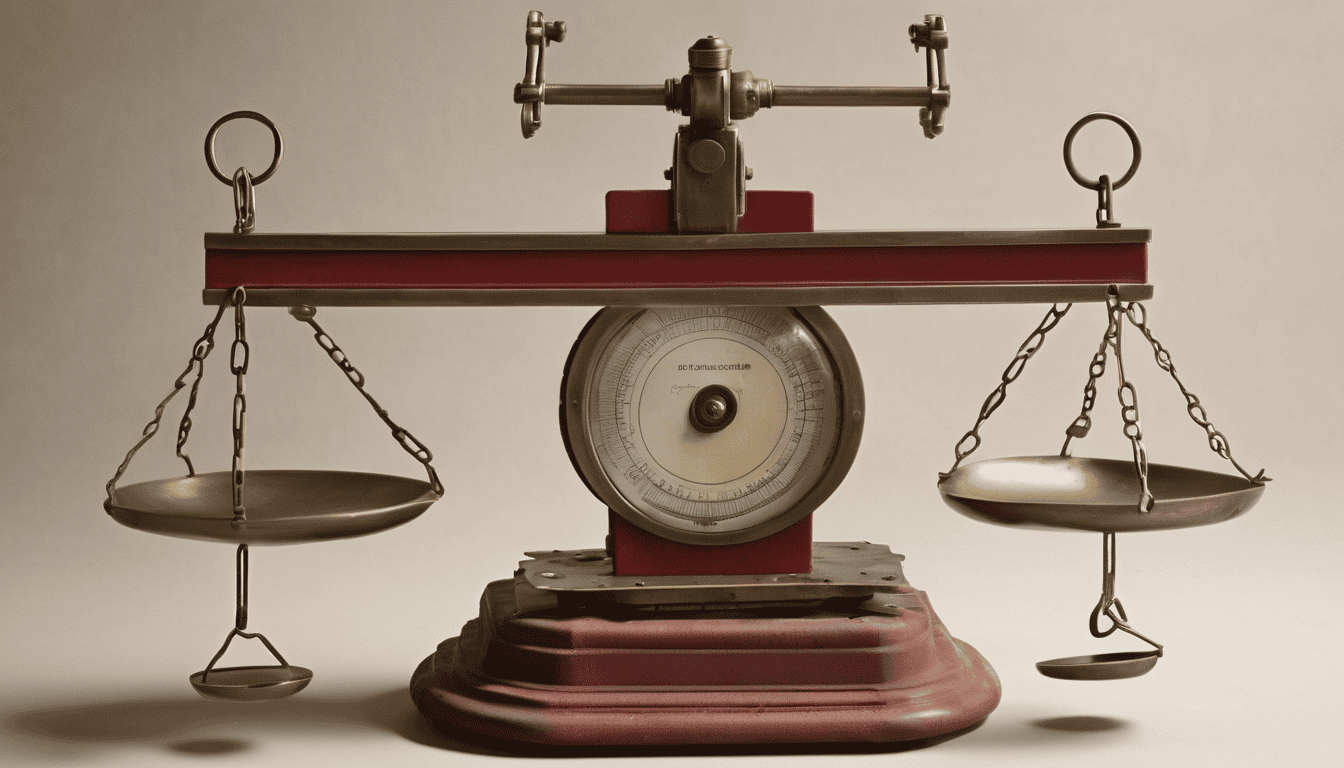










コメント