「なぜ、うまくいかなかったんだ。原因は誰だ」
プロジェクトが失敗に終わった時、あるいは目標が未達に終わった時。会議室に響くのは、未来に向けた建設的な議論ではなく、過去の責任を追及する詰問の声。多くの組織で繰り返されるこの光景は、単に「社風が古い」とか「マネジメントが下手だ」といった言葉で片付けられる問題ではありません。
実はその根底には、私たちの脳に備わった報酬システム、特に「ドーパミン」の働きが、極めて歪んだ形で利用されているという、深刻な病理が隠されています。
この記事では、失敗を許さず、常に「犯人探し」に終始する減点主義の組織文化が、いかにして社員の脳を「罰の快感」へとハックし、組織全体の挑戦意欲を根こそぎ奪っていくのか。そのメカニズムを、脳科学の観点から診断します。
本来のドーパミンの役割:「未来への期待」というエンジン
まず、世に流布する誤解を解くことから始めましょう。ドーパミンは、しばしば「快感物質」と説明されますが、その本質は、快感そのものではありません。ドーパミンの最も重要な役割は、「未来のより大きな報酬(快感)への期待」を生み出し、その目標に向かって行動を起こすための「意欲(モチベーション)」を掻き立てることです。
未知の課題に挑戦し、それを達成することで得られるであろう達成感や承認を「期待」する。この期待こそが、私たちを困難なタスクに向かわせる原動力なのです。つまり、健全な組織におけるドーパミンは、未来志向の挑戦と学習を促進する、極めて重要なエンジンとして機能します。
「罰の快感」へのハック:減点主義組織のドーパミン汚染
しかし、減点主義が支配する組織では、このドーパミンの働きが、まったく別の方向へと捻じ曲げられてしまいます。
失敗が許されず、常に責任追及の恐怖に晒されている環境では、社員は「未知への挑戦」から報酬を期待することができなくなります。なぜなら、挑戦は成功よりも失敗のリスクの方が遥かに高く、失敗すれば罰せられるからです。このような環境では、未来への期待を司るドーパミン回路は、機能不全に陥ります。
では、彼らのドーパミンは何に反応するようになるのでしょうか。皮肉なことに、それは「他者の失敗」と、それに伴う「罰」です。
自分が罰せられるリスクを回避し、相対的な安全を確保したいという強い欲求。この状況で、他者の失敗が明らかになり、その人物が「犯人」として特定され、罰せられる場面に遭遇した時、脳はそれを「自分が罰せられる脅威が去った」という報酬として解釈します。他者の失敗を指摘し、責任を追及するという行為そのものが、一時的な安堵感と優越感、すなわち「罰の快感」として、ドーパミンを放出させるように、脳がハッキングされてしまうのです。
「犯人探し」が自己目的化する負のスパイラル
一度この「罰の快感」の味を覚えた脳は、その報酬を求めて、さらに積極的に他者の粗探しや、失敗の証拠集めに動くようになります。こうして、組織内では「犯人探し」そのものが自己目的化していきます。
挑戦の回避
新しい挑戦は失敗のリスクを高めるため、誰もが前例踏襲の無難な仕事しかしなくなります。組織全体が、未知の可能性よりも、既知の安全性を優先するようになり、イノベーションの芽は摘み取られていきます。
情報の隠蔽
自分のミスは隠し、他者のミスは針小棒大に報告するという行動が、組織内での最も合理的な生存戦略となります。率直な報告や健全な情報共有は失われ、問題は発見が遅れ、より深刻化していきます。
部門間の対立
責任のなすりつけ合いが横行し、部門間の連携は困難になります。「誰のせいか」を巡る不毛な争いにリソースが割かれ、顧客や市場といった、本来向かうべき外部へのエネルギーが、内部へと消費されていきます。
マネジメント層がこの「犯人探し」ゲームの主審として振る舞い、誰かを罰することで自らの権威を確認するようになれば、事態は末期的です。組織のエネルギーは、未来の価値創造ではなく、過去の責任追及という、全く不毛な活動に費やされ、やがては挑戦する意欲そのものが組織文化から根絶されてしまうのです。
まとめ
本記事では、減点主義と犯人探しが蔓延る組織の病理を、脳科学の観点、特にドーパミン報酬系の汚染という視点から分析しました。
健全な組織が、未来への期待によってドーパミンを活性化させ、挑戦を促すのに対し、不健全な組織は、罰への恐怖を原動力とし、他者の失敗を罰することに快感を覚えるように、社員の脳をハッキングしてしまいます。この構造を理解せずして、組織文化の根本的な変革はあり得ません。
もしあなたの組織が、失敗を恐れ、挑戦をためらう空気に満ちているならば、それは個々の社員の意欲の問題ではなく、脳の報酬システムを歪める、組織全体の「病」の兆候かもしれません。まず診断すべきは、失敗が起きた時、あなたの組織が「未来の学習」と「過去の罰」、どちらにエネルギーを注いでいるか、という点です。






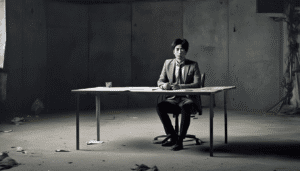
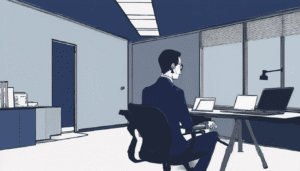



コメント