脳という「CPU」の処理能力には限界がある
人間の脳は、パーソナルコンピュータ(PC)の中枢処理装置(CPU)にたとえることができます。思考、判断、感情の制御といった高度な処理は、このCPUの働きによって行われます。そして、CPUの処理能力に物理的な限界が存在するように、私たちの脳が一度に処理できる情報量にも限りがあります。
現代社会、特にスマートフォンが生活の中心となって以降、私たちは常に膨大な情報に接続された状態にあります。起床から就寝まで、ニュースフィード、SNSの通知、メッセージアプリのやり取りが途切れることはありません。これは、PCで言えば、多数のアプリケーションを同時に起動し、常にバックグラウンドで稼働させている状態に相当します。
人間の脳は、本質的に複数の作業を同時に並行処理する「マルチタスク」を得意としていません。一般的にマルチタスクと呼ばれている状態は、実際には複数のタスク間を高速で切り替える「タスクスイッチング」です。その切り替えのたびに、脳には認知的な負荷がかかります。この負荷が、私たちの意識しないところで蓄積されていきます。これが、現代社会で指摘される「脳疲労」の基本的なメカニズムです。
情報過多が引き起こす「システムフリーズ」としてのパニック障害
PCのCPUに過剰な負荷がかかり続けると、処理速度が低下し、最終的にシステムが応答しなくなる「フリーズ」という状態に陥ることがあります。あるいは、システム保護のために強制的な再起動が行われます。これは、システムを保護するための安全装置が作動するためです。
このプロセスは、脳疲労がパニック障害へと至る過程と類似した点が見られます。継続的な情報のインプットは、脳、特に危険を察知し情動を司る扁桃体や、理性をコントロールする前頭前野に持続的なストレスを与えます。処理能力の限界を超えた脳は、いわゆる「オーバーヒート」にも似た、過負荷状態に陥ります。
この状態が続くと、自律神経系のバランスが崩れ、実際には危険がない状況にもかかわらず、身体が脅威に直面していると誤って信号を送ることがあります。これが、動悸、息苦しさ、めまいといった身体症状を伴うパニック発作の一因となる可能性があります。つまりパニック発作とは、過負荷に耐えられなくなった脳というシステムが引き起こす、一種の「システムフリーズ」あるいは「緊急停止」と解釈することができます。これは個人の精神的な強さや意志の問題ではなく、処理能力の限界を超えた情報入力に対する、脳の生理的な防御反応と捉えることが重要です。
なぜ私たちはインプットをやめられないのか
脳が疲弊していると認識していても、スマートフォンを手放すことが難しい背景には、社会的、そして心理的な要因が関係しています。
社会的要因:接続され続けることへの圧力
現代のコミュニケーションは即時性が重視され、常にオンラインであることが半ば常識となっています。仕事の連絡、プライベートの約束、社会の動向など、情報から切断されることへの漠然とした不安、いわゆる「見逃すことへの恐怖(FOMO: Fear of Missing Out)」が、私たちを常時接続へと促します。この社会的な圧力が、自発的に情報を遮断することを困難にしています。
心理的要因:ドーパミンと報酬系
新しい情報を得たり、SNSで肯定的な反応を得たりすると、脳内では快感物質であるドーパミンが放出されます。これは脳の「報酬系」を刺激し、一時的な満足感をもたらします。スマートフォンは、この報酬系を手軽に、そして繰り返し刺激するための効率的な装置です。この短いサイクルが反復されることで、無意識のうちに情報を求め続ける行動パターンが強化される可能性があります。
意図的な「シャットダウン」が脳を再起動させる
PCの動作不良を解消する最も基本的かつ効果的な方法は再起動です。そのためには、まず電源を落とす「シャットダウン」のプロセスが不可欠です。脳の過負荷状態を解消するためにも、同様に意図的な「シャットダウン」、すなわち情報のインプットを能動的に遮断する時間が必要となります。
情報のインプット環境を整理する
まず考えられるのは、受け取る情報の総量を物理的に減らすことです。使用頻度の低いニュースアプリや、時間を浪費しやすいゲームアプリを整理する。SNSやメッセージアプリのプッシュ通知をオフにし、自分が情報にアクセスするタイミングを主体的にコントロールする。このように情報環境を整備することで、脳のバックグラウンド処理を大幅に軽減することが可能です。
「何もしない時間」をスケジュールに組み込む
次に有効なのが、意識的に「何もしない時間」を確保することです。これは、単なる休憩とは異なります。スマートフォンやテレビ、書籍など、あらゆるインプットを遮断し、脳が内的な情報を整理するための時間です。散歩をする、入浴する、ただ窓の外を眺めるといった行為は、脳内でデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)と呼ばれる神経回路を活性化させます。このネットワークは、記憶の整理、自己認識、創造性の発揮において重要な役割を担っており、脳の機能を維持する上で不可欠です。生産性が重視される現代社会において「何もしない」ことには、非生産的という印象が伴うかもしれません。しかし、これは脳を健全な状態に保つための、極めて能動的で価値のある活動と位置づけることができます。
まとめ
現代社会における絶え間ない情報の流れは、私たちの脳を慢性的な過負荷の状態にさせています。この「脳疲労」が蓄積した結果、自律神経系の不調を引き起こし、パニック障害のような状態につながる可能性があります。
重要なのは、この問題を個人の精神的な弱さとして捉えないことです。これは、現代のテクノロジーと社会構造が、人間の脳の処理能力の限界を超えてしまったがゆえに生じている、構造的な課題です。
私たちのメディア『人生とポートフォリオ』では、パニック障害を単なる個人の問題としてではなく、現代社会が生み出す現象として捉え、その本質的な理解を目指しています。現在あなたが感じている不調は、あなた自身を責めるべきものではありません。
まずは、スマートフォンから少し距離を置き、意図的に情報を遮断する時間を数分でも確保してみてはいかがでしょうか。それは、過剰な負荷がかかったシステムを正常化させ、本来の穏やかな状態を取り戻すための、有効な第一歩となる可能性があります。
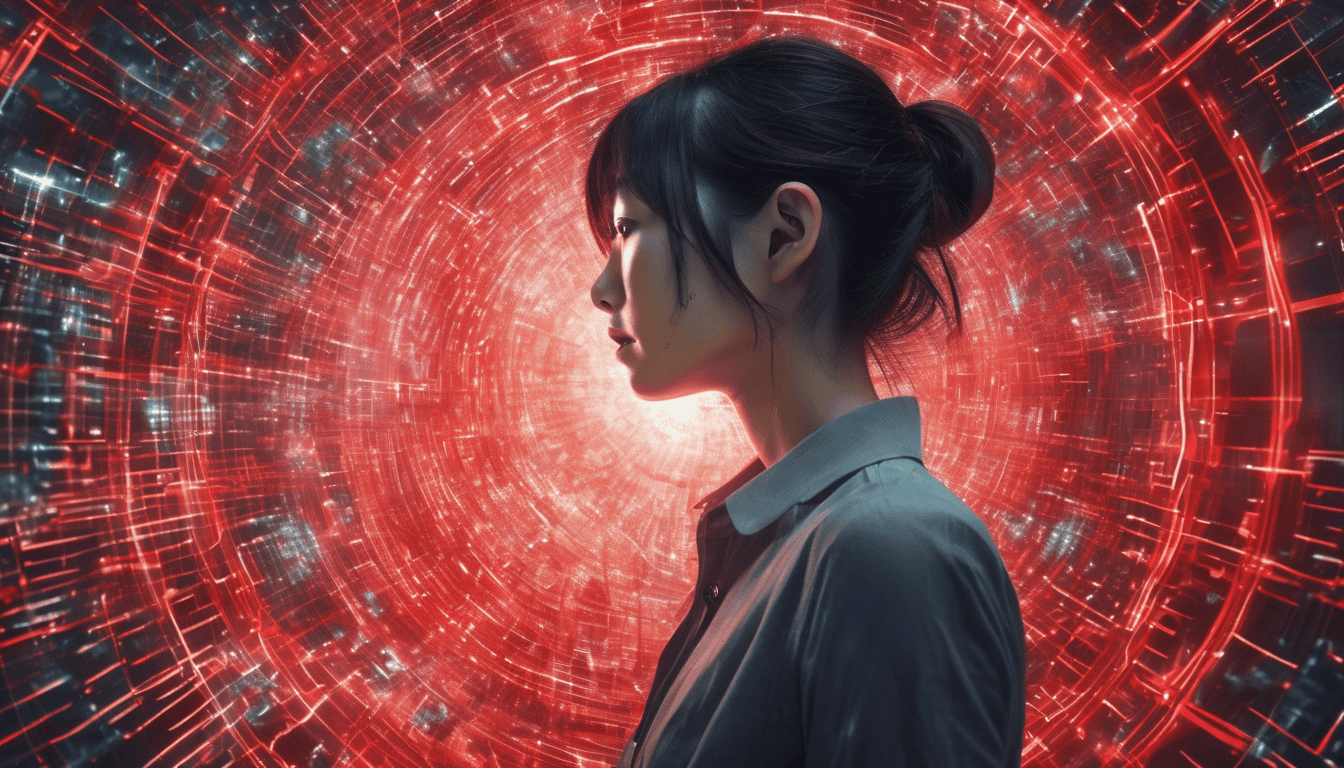


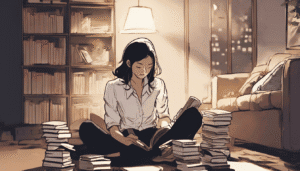

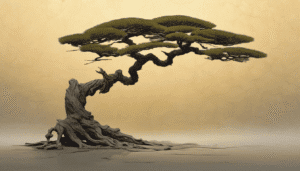

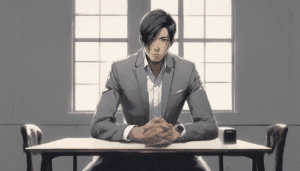


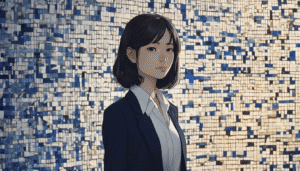
コメント