厳格な糖質制限を行い、良質なタンパク質を十分に摂取しているにもかかわらず、食後の血糖値が安定しない。こうした状況に直面している方もいるかもしれません。一般的に「血糖値を上げるのは糖質」「タンパク質は血糖値に影響しにくい」という認識は広く浸透していますが、人体の代謝メカニズムは多岐にわたります。
当メディア『人生とポートフォリオ』では、健康をあらゆる活動の基盤となる重要な「健康資産」と位置づけています。今回は、食生活に関するより深い理解を求める方へ、タンパク質と血糖値の関連性について解説します。
この記事では、高タンパクな食事が血糖値を上昇させる可能性がある背景の「糖新生」という仕組みを解説し、ご自身にとっての適切なバランスを見つけるための視点を提供します。
血糖値の恒常性と糖新生の役割
まず、私たちの体がエネルギーをどのように調節しているか、その基本原則から確認します。食事から摂取した糖質は、体内でブドウ糖に分解され、血液中を移動します。これが血糖です。血糖値が上昇すると、膵臓からインスリンというホルモンが分泌され、ブドウ糖を細胞に取り込むことでエネルギーとして利用したり、グリコーゲンとして肝臓や筋肉に貯蔵したりします。これが、血糖値調節の基本的な仕組みです。
ここで関連するのが、本記事の主題である「糖新生」です。
糖新生とは、「糖を新たに生み出す」体の仕組みを指します。具体的には、糖質以外の物質を材料にして、主に肝臓でブドウ糖を合成するプロセスです。この材料となるのが、運動時に筋肉で発生する乳酸や、中性脂肪が分解されて生じるグリセロール、そしてタンパク質を構成するアミノ酸です。
糖新生は、体にとって異常な反応ではありません。空腹時や長時間の運動時など、食事からの糖質供給が減少した際に、脳をはじめとする重要な臓器に安定してエネルギーを供給し、血糖値を一定に保つための、重要な生命維持機能です。
タンパク質の過剰摂取が血糖値を上昇させるメカニズム
生命維持に重要な役割を持つ糖新生が、なぜ特定の条件下で血糖値を上昇させてしまうのでしょうか。その要因は、「材料の供給量」と「インスリンの機能」に関連しています。
余剰アミノ酸と糖新生の関係
食事から摂取したタンパク質はアミノ酸に分解された後、筋肉や内臓、皮膚、ホルモンなどの材料として利用されます。しかし、体が必要とする量には上限があります。
体内で材料として使われず、エネルギーとしても消費されなかった余剰のアミノ酸は、そのまま体内に蓄積されるわけではありません。その一部が、肝臓で糖新生の材料として利用されることがあります。つまり、タンパク質を過剰に摂取することは、糖新生の基質を供給することにつながり、結果として血糖値を上昇させる一因となる可能性があります。
インスリン機能との関連性
インスリンが正常に機能している場合、タンパク質を摂取しても、この糖新生による血糖値の上昇は適切に調節されます。タンパク質の摂取は、血糖値を下げるインスリンだけでなく、血糖値を上げるグルカゴンというホルモンの分泌も促します。この二つのホルモンが均衡を保つことで、血糖値は比較的安定した状態に維持されます。
しかし、1型糖尿病の方や、長年の生活習慣によってインスリンの分泌能力が低下している方、あるいは細胞がインスリンに反応しにくくなる「インスリン抵抗性」が存在する場合、状況は異なります。糖新生によって新たに作られたブドウ糖が血中に放出されても、それを適切に処理するためのインスリンが不足、あるいは機能不全に陥っているため、血糖値の上昇を十分に抑制できないことがあります。
厳格な糖質制限をしているにもかかわらず、タンパク質を一度に大量摂取した後に血糖値が上昇する現象は、このメカニズムが影響している可能性があります。
個々に最適なタンパク質摂取量を見極める方法
では、タンパク質とどのように向き合えば良いのでしょうか。重要なのは、タンパク質を問題視するのではなく、ご自身の体にとっての「最適な量」を見極めるという視点です。
一般的な推奨量と個別性の考慮
一つの目安として、厚生労働省が示すタンパク質の推奨量は、多くの成人で体重1kgあたり1.0g程度です。しかし、これは集団を対象とした平均的な指標です。最適なタンパク質量は、年齢、性別、日々の活動量、そして先述したインスリン機能といった、個人的な要因によって変動します。
画一的な基準を求めるのではなく、自分自身の状態を客観的に観察し、最適なバランスを調整していくアプローチが求められます。
客観的データに基づく個別のアプローチ
ご自身の体にとっての適切な量を知るための一つの有効な方法は、実際に測定し、その反応を記録することです。持続血糖測定器(CGM)などを活用できる方は、タンパク質の摂取量と食後の血糖値の変動をデータとして可視化することを検討してみてはいかがでしょうか。
例えば、一食あたりのタンパク質量を20g、30g、40gと段階的に変更し、それぞれの食後2〜3時間の血糖値がどのように推移するかを観察します。これにより、「自身の体は、タンパク質が一定量を超えると血糖値に影響が出始める」といった、個人に特化した知見を得ることが可能です。このような自己観察に基づく調整は、画一的な情報に依存せず、自身の健康を主体的に管理するための方法の一つです。
まとめ
本記事では、タンパク質の過剰摂取が「糖新生」というメカニズムを通じて血糖値を上げる可能性について解説しました。特にインスリンの機能が十分でない方にとって、この視点は日々の血糖管理を再考する上で参考になるかもしれません。
- タンパク質も、体内で過剰になれば糖新生の材料となり、血糖値を上昇させる一因となり得ます。
- この現象は体の正常な調節機能ですが、インスリン分泌能が低下している場合は、血糖コントロールに影響を与えることがあります。
- 解決策は、タンパク質を避けることではありません。自身の活動量や体の反応を客観的に観察し、「自分にとっての適切なバランス」を見つけ出すことです。
これは、当メディアが提唱する「ポートフォリオ思考」にも通じます。資産形成において株式や債券への集中投資がリスクを高めるように、栄養素においても特定の何かに偏重することは、体のバランスを損なう可能性があります。
健康という重要な資産を守り育てるためには、断片的な知識に左右されるのではなく、自身の体と向き合い、全体としての最適なバランスを追求し続ける姿勢が不可欠です。この記事が、そのための新たな視点となれば幸いです。
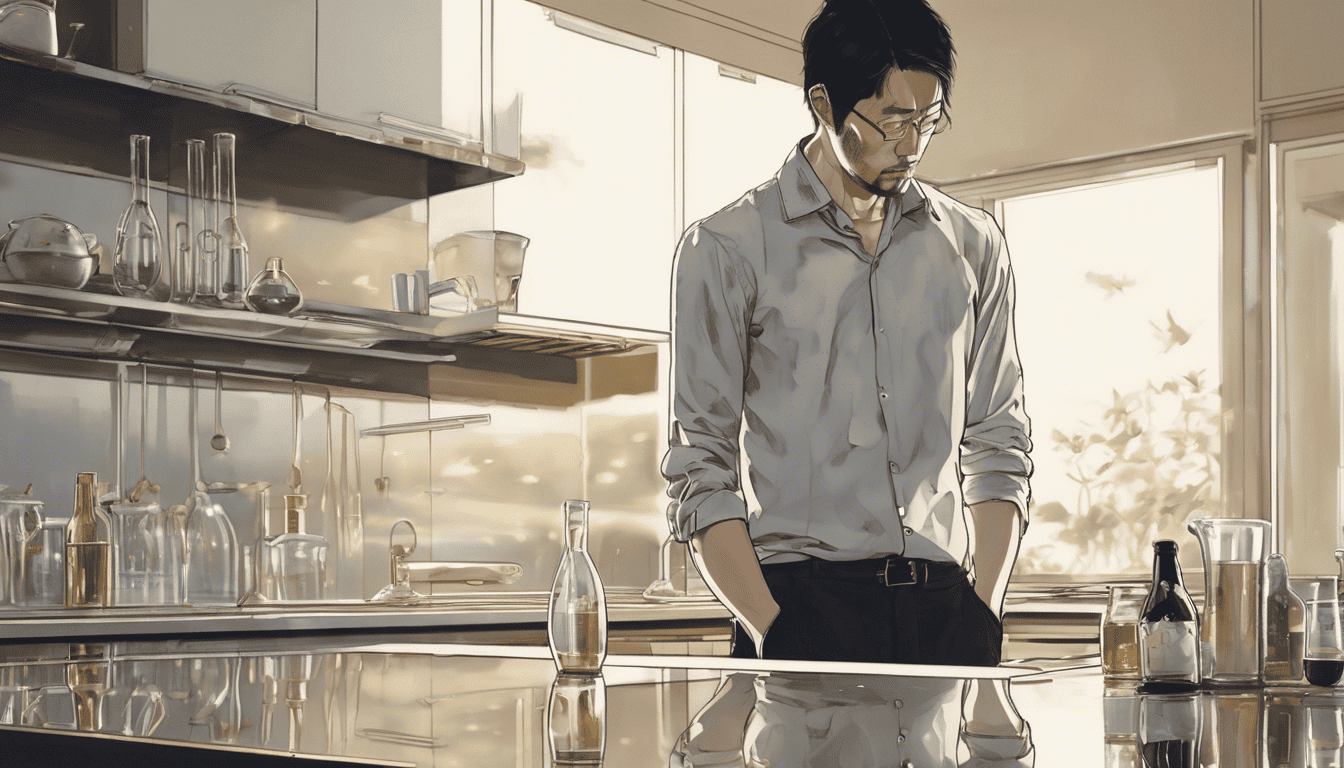










コメント