てんかんの症状を持つ方が、ご自身の状態と向き合う中で、発作の誘因を可能な限り減らしたいと考えるのは自然なことでしょう。一般的に、睡眠不足や過度なストレス、光の点滅などが発作の誘因として知られており、日常生活で注意を払っている方も少なくありません。
しかし、なぜ私たちは目に見えやすい外部の要因には注意を払う一方で、自身の体内環境、特に「食事」や「血糖値」が脳の状態に与える影響については、見過ごしがちなのでしょうか。
当メディア『人生とポートフォリオ』では、人生を構成するあらゆる資産の中でも、全ての活動の基盤となる「健康資産」を最も重要な土台と位置づけています。心身の安定なくして、良質な思考や豊かな人間関係、長期的な資産形成を築くことは難しいでしょう。
この記事では、てんかん発作と血糖値、特に「低血糖」との関係性に焦点を当てます。血糖値の安定が、発作を管理するための重要な自己管理法の一つとなり得る、という視点を提示します。日々の生活に潜む要因を理解し、より穏やかな毎日を送るための知識としてお役立てください。
てんかん発作と脳の電気的興奮
まず、てんかん発作がどのようにして起こるのか、その基本的な仕組みから確認します。私たちの脳は、数千億個ともいわれる神経細胞(ニューロン)が、微弱な電気信号をやり取りすることで機能しています。通常、この電気信号は規則正しく、秩序を保った状態で伝達されています。
てんかん発作とは、この脳の神経細胞の一部が、何らかの原因で突然、過剰かつ無秩序な電気的興奮を起こす現象です。この異常な電気活動が脳のどの部分で起こるかによって、意識の消失や体のけいれんなど、様々な症状として現れます。
睡眠不足やストレスが発作の誘因となり得るのは、それらが脳の神経系のバランスを乱し、神経細胞を興奮しやすい状態、つまり発作が起こりやすくなる状態にするためと考えられています。そして、これらと同様に、脳の神経細胞の状態に直接的な影響を与えるもう一つの重要な要素が、エネルギー源である血糖値です。
低血糖状態と脳の過敏性
血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)の濃度のことです。脳は私たちの体の中で最も多くのエネルギーを消費する器官であり、その主要なエネルギー源は、このブドウ糖です。
安定した脳機能は、血液から安定的に供給されるブドウ糖によって支えられています。では、このエネルギー供給が不安定になる「低血糖」の状態では、脳に何が起こるのでしょうか。
なぜ低血糖は神経細胞を不安定にするのか
低血糖とは、血液中のブドウ糖濃度が異常に低下した状態を指します。これは、脳にとってのエネルギー供給が滞ることを意味するため、脳機能に直接的な影響を及ぼします。
具体的には、エネルギー不足に陥った神経細胞は、細胞膜の電位を正常に保つ能力が低下します。細胞の内外のイオンバランスが崩れやすくなり、神経細胞全体が非常に不安定で過敏な状態に置かれます。
この過敏な状態は、わずかな刺激でも過剰な電気的興奮を起こしやすい状態と言い換えることができます。したがって、てんかんの素因を持つ方にとって、低血糖は脳の異常な電気活動を誘発する直接的な引き金となる可能性があるのです。
てんかんを持つ方が特に注意すべき血糖値の変動
健康な人であっても、低血糖は冷や汗、動悸、強い空腹感などの身体的症状や、集中力の低下、意識の混濁といった精神的症状を引き起こします。てんかんの症状を持つ方の場合、その影響はより大きなものとなる可能性があります。
特に注意が必要なのは、食事の内容によって引き起こされる急激な血糖値の変動です。例えば、空腹時に甘い菓子類や清涼飲料水などを大量に摂取すると、血糖値は一時的に急上昇します。すると、体は血糖値を下げるためにインスリンというホルモンを大量に分泌し、その結果、逆に血糖値が急降下して「反応性低血糖」に陥ることがあります。
このような血糖値の乱高下は、脳へのエネルギー供給を極めて不安定にし、神経細胞に大きな影響を与えます。これが、てんかん発作のリスクを高める一因になると考えられています。
食事を通じた血糖値の安定化というアプローチ
てんかんと低血糖の関係を理解すると、日々の食事を通じて血糖値を安定させることが、発作の予防においていかに重要であるかが見えてくるのではないでしょうか。これは、薬物治療や生活習慣の改善に加え、自分自身で取り組むことのできる、積極的な自己管理法の一つとなり得ます。
血糖値を急上昇させない食事の基本
血糖値の急激な変動を避けるための食事の基本は、糖質の「量」と「質」を意識することです。
GI(グリセミック・インデックス)値という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは、食後の血糖値の上昇度合いを示す指標です。精製された白米や食パン、砂糖といった高GI食品は、摂取すると血糖値を急激に上昇させます。
一方で、玄米や全粒粉パン、豆類、葉物野菜などの低GI食品は、糖質の吸収が緩やかで、血糖値の上がり方も穏やかです。日々の食事で高GI食品を避け、低GI食品を中心に献立を組み立てることが、血糖値安定の第一歩となります。
また、食事の順番を工夫する「ベジタブルファースト(野菜から先に食べる)」や、一度の食事量を減らして食事の回数を増やす「分割食」なども、血糖値の急上昇を抑えるのに有効な方法とされています。
なぜ「ケトン食療法」がてんかん治療に用いられるのか
てんかんの治療法の一つに、「ケトン食療法」という食事療法が存在します。これは、極端に糖質の摂取を制限し、その代わりに脂質を多く摂取することで、体のエネルギー源をブドウ糖から「ケトン体」に切り替えることを目的としたものです。
このケトン食療法がなぜ有効と考えられているのか、その理由の一つが血糖値の安定化です。糖質の摂取がほとんどないため、血糖値の変動が極めて小さくなります。
さらに、脳がエネルギー源としてケトン体を主に利用するようになると、神経細胞の興奮を抑制する効果や、神経を保護する作用があることが研究で示唆されています。つまり、ケトン体はブドウ糖よりも安定したエネルギー源として機能し、脳の過剰な電気的興奮そのものを起こしにくくする可能性があるのです。
ただし、ケトン食療法は栄養バランスの管理が難しく、副作用のリスクも伴う専門的な治療法です。必ず専門の医師や管理栄養士の指導のもとで行う必要があり、専門家の指導なく自己判断で始めることは避けるべきです。
日常生活で血糖値の安定を意識するために
てんかん発作の管理は、多角的なアプローチが求められます。これまで意識してきた睡眠やストレスの管理に、「血糖値の安定」という新たな視点を加えてみてはいかがでしょうか。
まずは、日々の食事内容と、その後の体調の変化を簡単に記録することから始めることが考えられます。どのような食事をした後に、眠気やだるさ、あるいは気分の変動を感じやすいか。自身の体の反応に意識を向けることで、自分にとって血糖値を乱しやすい食事のパターンが見えてくることがあります。
持続血糖測定器(CGM)などで血糖値の動きを詳細に把握する方法もありますが、まずは日々の食事内容を見直すことから着手することが、実践的な第一歩となり得ます。
まとめ
この記事では、てんかん発作の誘因として見過ごされがちな「血糖値」、特に「低血糖」との関係性について解説しました。
脳の主要なエネルギー源であるブドウ糖が不足する低血糖状態は、脳の神経細胞を過敏にし、異常な電気的興奮が起こりやすい環境を作り出します。これは、てんかんの症状を持つ方にとって、発作の直接的な誘因となる可能性があります。
日々の食事内容を意識し、血糖値の急激な変動を避けることは、従来の睡眠管理やストレス対策と並ぶ、重要な自己管理法の一つです。食事の質や食べ方を工夫すること、そして、てんかん治療における食事療法(ケトン食など)の背景にある論理を理解することは、ご自身の状態を主体的に管理していく上で、一つの視点となるでしょう。
当メディアが繰り返しお伝えしているように、全ての土台は「健康資産」です。心身のコンディションを良好に保つことこそが、人生における様々な選択肢と可能性を広げるための、極めて重要な基盤となります。この記事が、あなたの健康資産を守り、より穏やかな日々を築くための一助となれば幸いです。
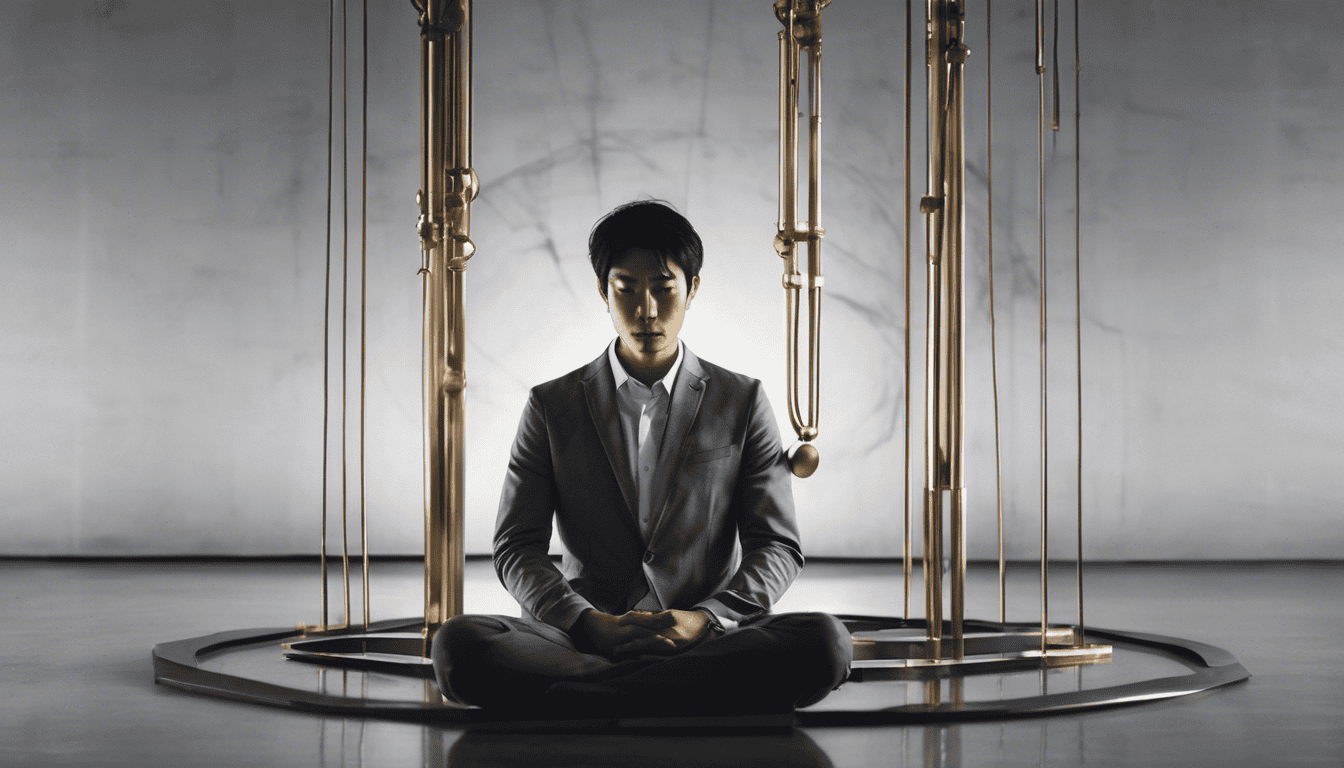










コメント