子供の頃に食べたお菓子やパンについて、特定の風景と結びついた「味」の記憶を持つ人は少なくありません。しかし、何年も経過してから同じ製品を口にした時、「昔はもっと美味しかった」という感覚を抱くことがあります。
この感覚は、個人の味覚が変化した可能性と、製造者が製品の味を変えた可能性という、二つの側面から考えることができます。この問いは、単なる懐古的な感情に留まらず、私たち個人の内的な変化と、社会という外的な変化の接点を考察するきっかけとなります。
本稿では、この「昔の製品は味が変わった」と感じる現象の背景を、多角的に分析します。これは、私たちの記憶の中に存在する「絶対的な味」という概念を見直し、変化し続ける現在を理解するための一つの試みです。
味が変わったと感じる個人の内的要因
まず考察すべきは、私たち自身の身体的、心理的な変化です。味の感じ方は、決して不変のものではありません。
年齢と共に変化する味覚の生理学
人間の味覚を司る器官である舌の味蕾(みらい)は、約10日という短い周期で新しい細胞に再生されます。しかし、加齢と共にこの新陳代謝の速度は緩やかになり、味蕾の数そのものも減少する傾向があります。
これにより、特に甘味や塩味といった基本的な味覚に対する感受性が変化することが指摘されています。子供の頃に強く感じた甘さが、大人になってからは適度に感じられたり、あるいは物足りなく感じられたりするのは、この生理学的な変化が一因である可能性が考えられます。つまり、製品が変わったのではなく、味を受け取る側の私たち自身が、生物学的に変化しているのです。
経験が形成する「記憶の味」
味覚は、純粋な化学的感覚だけによって構成されるものではありません。それは、食事をした時の状況、感情、環境といった文脈情報と強く結びついて記憶されます。心理学における「エピソード記憶」として保存された味は、単なる味覚情報以上の意味合いを持ちます。
肯定的な思い出と共にあった味は、記憶の中でより好ましいものとして記録されがちです。この「ノスタルジア・バイアス」は、過去の味を実際以上に特別なものとして認識させる効果を持ちます。したがって、成人してから同じ製品を食べても、その背景にある「特別な文脈」が再現されないため、かつてと同等の感動を得ることが難しくなります。私たちが求めているのは、純粋な味そのものではなく、その味に付随していた肯定的な体験の再現である可能性があります。
味が変わった背景にある社会の外的要因
私たちの内的な変化と並行して、製品を取り巻く外部環境も絶えず変化しています。製造者が「昔ながらの味」を維持し続けることには、多くの複雑な課題が伴います。味の変化の背景には、時代の要請に応えるための、企業の合理的な判断が存在します。
消費者の健康志向による影響
現代社会において、消費者の健康に対する意識は著しく高まっています。糖分や塩分の摂取が健康に与える影響に関する情報が広く共有される中で、食品製造者は製品の成分を見直す必要に迫られています。
「減糖」「減塩」「カロリーオフ」といった表示は、製品選択における重要な基準の一つです。製造者は、こうした消費者の需要に応えるため、砂糖や塩の使用量を調整し、代替甘味料や新たな調味料を導入します。この調整は、製品の基本的な味の構成に影響を与えます。私たちが感じる味の変化は、社会全体の価値観の変化を反映したものであり、消費者自身が望んだ変化の結果と捉えることもできます。
原材料費高騰とサプライチェーンの変容
製品に使用される小麦粉、砂糖、油脂、カカオといった原材料の価格は、天候不順や国際情勢、為替変動といった要因によって常に変動しています。特定の産地の原材料が供給不足に陥ったり、輸入コストが急騰したりした場合、製造者は製品価格を維持するために、代替原材料の利用や配合比率の変更を検討せざるを得ません。
また、安定した品質と供給量を確保するために、特定の供給元への依存を避けるサプライチェーンの最適化も進められています。これは企業経営の観点からは合理的な戦略ですが、原材料の産地や品種がわずかに変わるだけで、製品の風味には差異が生じる可能性があります。
製造プロセスと効率化の論理
製品を安定的に、かつ経済的な価格で大量に供給し続けるためには、製造プロセスの効率化が不可欠です。新しい製造機械の導入や生産ラインの自動化は、品質の均一化とコスト削減に寄与します。
しかし、こうしたプロセスの変更が、結果として味に影響を与えることがあります。例えば、生地の混練時間や発酵温度、焼成方法などが近代的な設備に合わせて最適化される過程で、旧来の製法が持っていた特定の食感や風味が変化する可能性は否定できません。また、保存性の向上や製造効率の改善を目的として使用される食品添加物が変更されることも、味の変化の一因となり得ます。
「失われた味」とは過ぎ去った「時代」の反映である
ここまで見てきたように、「昔の製品の味が変わった」という感覚は、個人の内的変化と、社会・経済の外的変化が複雑に作用し合った結果として生じる現象です。私たちの記憶の中にある「あの頃の味」は、特定の時代の、特定の条件下でのみ成立し得た、偶有的な産物であったと言えます。
それは、健康への配慮が現在とは異なっていた時代の味であり、特定の原材料が安定的に確保できた時代の味であり、そして何よりも、私たち自身が今とは違う感受性を持っていた時代の味です。つまり、「失われた味」を求めることは、過ぎ去った「時代」そのものを求めていることと等しいのかもしれません。
このメディアでは、人生を構成する様々な要素を、変化し続けるポートフォリオとして捉える視点を提示しています。思い出の味もまた、私たちの人生のポートフォリオを構成する一つの要素ですが、それは固定された資産ではありません。時代と共にその価値や意味合いが変容していく、流動的な存在なのです。
まとめ
久しぶりに口にした食品の味に違和感を覚える時、それは自分自身と、自分を取り巻く世界が不可逆的に変化したという事実を認識する瞬間でもあります。
その要因は、味蕾の減少といった生理学的なものから、ノスタルジアという心理的なもの、さらには健康志向の高まりや原材料費の高騰といった社会経済的なものまで多岐にわたります。記憶の中の味は、絶対的な基準ではなく、ある特定の時空間にのみ存在した、再現不可能な体験であると理解できます。
過去の味に対する固執を手放すことは、喪失を認めることとは異なります。それは、変化こそが常態であるという事実を受け入れ、過去の記憶を尊重しつつも、「今、ここにある味」を新たな基準として楽しむという、より建設的な姿勢を持つことにつながります。失われた味に思いを馳せながらも、今日口にする製品の中に、新しい時代の味と、新しい自分自身を発見すること。この視点を持つことが、変化し続ける社会に適応していくための一つの方法となり得ます。







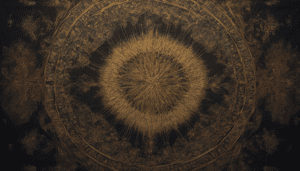



コメント