現代の私たちは、健康に関する情報に日々触れています。新しいスーパーフード、革新的なサプリメント、最新のトレーニング理論。健康になるためには、何か新しい、特別なものを生活に「足す」必要があるという考え方が、広く浸透しているように見受けられます。しかし、もしその答えが未来のテクノロジーではなく、人類の遥かなる「過去」に隠されているとしたら、どうでしょうか。
本記事では、私たちのメディア『人生とポートフォリオ』が探求する「血糖値」という大きなテーマの一環として、歴史と比較という視点から、現代の健康問題を捉え直します。具体的には、農耕が始まる以前の狩猟採集民の生活様式に光を当て、なぜ彼らの間では現代で言うところの糖尿病がほとんど存在しなかったのかを考察します。
この記事が目指すのは、単なる過去への懐古ではありません。現代の食生活や身体活動が、人類の遺伝子が本来想定していた状態からいかに乖離しているかを理解し、私たちの健康観を根底から見直すための視点を提供することです。
現代に広がる「血糖値の問題」とは何か
本題に入る前に、現代社会における「血糖値の問題」について、その本質を整理しておく必要があります。血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことです。食事を摂ると血糖値は上昇し、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの働きによって、ブドウ糖はエネルギーとして細胞に取り込まれ、血糖値は安定した状態に戻ります。
しかし、精製された炭水化物や糖分を過剰に摂取する現代的な食生活は、この仕組みに大きな負荷をかけます。食事のたびに血糖値が急激に上昇と下降を繰り返す「血糖値スパイク」や、インスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」という状態を引き起こす可能性があります。このインスリン抵抗性が進行した先にあるのが、2型糖尿病です。
これは、食生活だけの問題ではありません。デスクワークが中心となり、移動は車や電車に依存する現代のライフスタイルは、慢性的な運動不足をもたらします。身体活動の減少は、インスリンの感受性を低下させる一因となり、血糖値のコントロールをさらに難しくしています。
「狩猟採集民」の生活様式と血糖値の安定
それでは、時計の針を大きく巻き戻し、狩猟採集民の生活を見てみましょう。彼らの日常は、現代とは全く異なる環境にありました。そして、その生活様式そのものが、血糖値を安定させるための極めて合理的なシステムとして機能していたことが、近年の研究から示唆されています。
食生活:何を、どのように食べていたか
狩猟採集民の食卓に、現代のスーパーマーケットに並ぶような加工食品や精製された砂糖、穀物はありませんでした。彼らの栄養源は、狩猟によって得られる動物の肉や魚、そして採集した木の実、種子、根菜、葉物野菜、季節の果物といった、加工されていない自然食品そのもの、いわゆる「ホールフード」でした。
これらの食物は、食物繊維を豊富に含んでいます。食物繊維は糖の吸収を緩やかにするため、食後の血糖値の急上昇を抑制する働きがあります。タンパク質や脂質を中心とした食事構成も、血糖値の安定に寄与していたと考えられます。彼らの食事は、結果として極めて低グリセミック・インデックス(GI)なものであったと言えるでしょう。
身体活動:日常に組み込まれた運動
彼らにとって、身体を動かすことは「エクササイズ」や「トレーニング」といった特別な活動ではありませんでした。それは、生きることそのものでした。食料を得るための狩りや採集、安全な寝床への移動、水汲みなど、日常のあらゆる場面で体を動かすことが求められました。
このような恒常的な身体活動は、筋肉が血液中のブドウ糖をエネルギーとして効率的に利用するのを助け、インスリン感受性を高いレベルで維持します。現代人がフィットネスジムで意図的に行っている運動を、彼らは生活の一部として、ごく自然に行っていたのです。
食事のタイミング:「食べない時間」の存在
現代のように、1日3食が保証され、いつでも軽食が手に入る環境は、人類の歴史から見れば極めて異例です。狩猟採集民の生活では、狩りの成果や天候によって、食事ができない日も珍しくありませんでした。
この「食べない時間」、すなわち意図せぬ断食(ファスティング)が、彼らの健康に重要な役割を果たしていた可能性があります。食事をしない時間帯には、インスリンの分泌が抑制され、細胞はインスリンに対する感受性を回復させます。また、細胞が自らを浄化し、新しく生まれ変わる「オートファジー」という仕組みが活性化することも知られています。この周期的な休息が、代謝システム全体を健全に保っていたのかもしれません。
私たちの遺伝子が記憶する「本来の姿」
人類が地球上に誕生してからの歴史を24時間とすると、農耕牧畜が始まったのは最後の約5分間、産業革命以降の時間はわずか数秒に過ぎません。私たちの遺伝子、すなわち身体の基本的な設計図は、その時間の99%以上を占める狩猟採集時代に適応するよう、長い年月をかけて形作られてきました。
この事実と、現代の生活環境との間には、大きな「ミスマッチ」が存在します。私たちの身体は、カロリーが乏しく、常に体を動かす必要があった環境を前提としています。しかし、現代社会は高カロリーの食事が容易に手に入り、身体を動かす機会が極端に少ない環境です。
このミスマッチこそが、糖尿病を含む多くの生活習慣病の根源的な要因である、というのが「ミスマッチ仮説」の考え方です。私たちの遺伝子は、この急激な環境変化にまだ追いついていないと考えられています。
現代の生活に「引き算」の発想を取り入れる
狩猟採集民の生活を完全に模倣することは不可能ですし、その必要もありません。しかし、彼らの生活様式から、現代の健康問題に対処するための本質的なヒントを学ぶことはできます。それは、「何かを足す」という発想から、「不自然なものを取り除く」という「引き算」の発想への転換です。
加工食品や精製糖質を「減らす」
まず着手できることとして、狩猟採集民が決して口にしなかったであろう、超加工食品や精製された砂糖、清涼飲料水を日常生活から意識的に減らしていくことが考えられます。自然な食材そのものを味わう食事に切り替えることは、血糖コントロールの第一歩です。
「食べる時間」を意識し、「食べない時間」を設ける
1日のうち、食事をする時間を8時間から12時間の間に設定し、残りの時間は固形物を摂らない「食べない時間」を作ることも、現代的に応用可能な方法の一つです。これにより、インスリン感受性の回復を促し、消化器官を休ませることができます。
日常の中に「動き」を組み込む
エレベーターを階段に変える、一駅手前で降りて歩く、少し遠くのスーパーまで歩いて買い物に行く。このような小さな工夫の積み重ねが、日常の活動量を増やし、血糖値の安定に貢献します。特別な運動時間を確保するだけでなく、生活の中に「動き」を溶け込ませるという視点が重要です。
まとめ
本記事では、狩猟採集民の生活様式を振り返ることで、現代の糖尿病をはじめとする血糖値の問題を考察しました。彼らの生活には、加工食品や精製糖質が存在せず、日常的な身体活動が豊富で、自然な「食べない時間」が存在していました。この環境こそが、私たちの遺伝子が本来、最適化されている状態に近いのかもしれません。
もしあなたがこれまで、「健康になるには何か新しいものを足さなければならない」と考えていたとしたら、一度立ち止まってみてください。解決の糸口は、未来の技術や未知の成分ではなく、人類が経験してきた長い歴史の中に、静かに存在している可能性があります。
当メディア『人生とポートフォリオ』では、健康を人生における最も重要な「資産」の一つと捉えています。血糖値の問題に向き合うことは、この根源的な健康資産を守り、育てるための本質的なアプローチです。それは、未来への不安から何かを付け足していく作業ではなく、私たちの身体が記憶している本来の姿へと、少しずつ還っていく知的な探求と言えるでしょう。
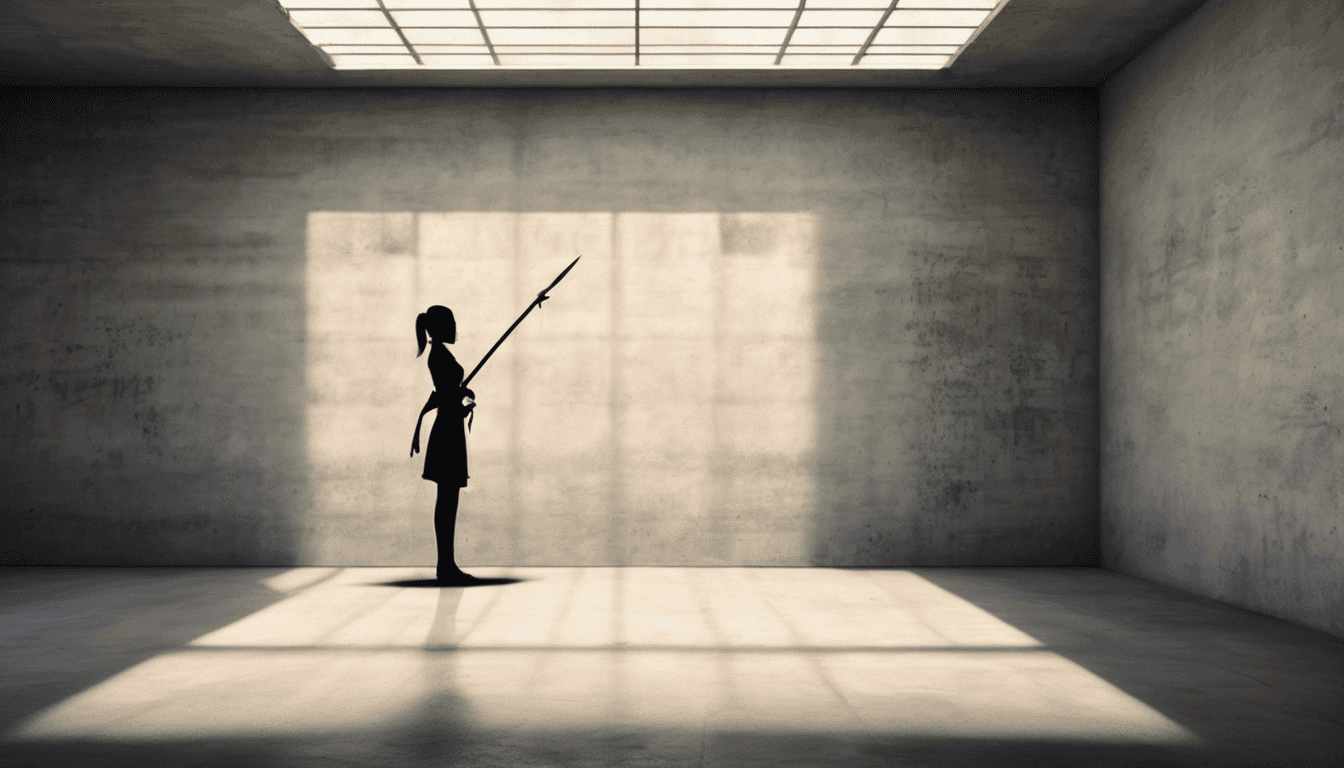










コメント