私たちの食卓にのぼる魚。スーパーの鮮魚コーナーで、「天然」と書かれたものと「養殖」と書かれたものが並んでいる光景は、日常の一部になっています。多くの人が、「天然の魚は安全で美味しく、養殖の魚には何らかの不安がある」という漠然としたイメージを抱いているのではないでしょうか。特に健康への意識が高い方ほど、養殖魚に関する情報を見聞きし、選択をためらった経験があるかもしれません。
しかし、そのイメージは現代の実態を正確に反映しているのでしょうか。「天然=善、養殖=悪」という単純な二元論は、私たちが本質的な選択をする機会を狭めている可能性があります。
当メディア『人生とポートフォリオ』では、人生を構成する要素を「資産」として捉え、その最適な配分を目指す思考法を提案してきました。食事とは、私たちの最も根源的な資本である「健康資産」に対する、日々の投資活動に他なりません。だからこそ、食品を選ぶ際には、表面的なイメージに影響されるのではなく、その背景にある構造を理解し、多角的な視点から判断するリテラシーが求められます。
この記事では、「天然」と「養殖」それぞれが抱えるリスクとメリットを客観的に比較し、私たちがより持続可能で安全な魚を選び抜くための、新たな判断基準を提示します。
天然魚が抱える潜在的リスクの検証
まず、多くの人が信頼を寄せる傾向にある「天然」という選択肢について、その内実を検証します。広大な海を自由に泳いでいた魚は、自然の産物であることに違いありません。しかし、その海洋環境がもはや人為的な影響と無縁ではないという現実を考慮に入れる必要があります。
海洋汚染物質のリスク:マイクロプラスチックと重金属
現代の海洋環境は、人間活動によって排出された様々な化学物質にさらされています。その代表的なものとして、マイクロプラスチックと重金属が挙げられます。
マイクロプラスチックは微細なプラスチック粒子であり、海洋生物が餌と誤認して摂取することが問題視されています。これらが食物連鎖を通じて魚の体内に取り込まれ、最終的に私たちの食卓に届く可能性が指摘されています。
また、水銀などの重金属による汚染も懸念されます。工場排水などに含まれる重金属は、食物連鎖の過程で上位の捕食者ほど体内に高濃度で蓄積されていく傾向があります。この現象は「生物濃縮」と呼ばれます。そのため、マグロやカジキ、キンメダイといった大型の魚ほど、水銀の含有量が高くなる可能性があります。特に、胎児への影響が懸念されるため、妊婦の方々には厚生労働省から摂取量に関する注意喚起がなされています。
資源枯渇という構造的問題
もう一つの側面は、サステナビリティ、つまり持続可能性の問題です。世界的な魚介類の需要増加に伴い、多くの魚種が乱獲によって資源量を減少させています。私たちが「天然」の魚を消費し続けることが、将来世代が利用できる海洋資源を減少させる行為につながる可能性も否定できません。
「天然」という表示は、必ずしも環境に対して責任ある選択を保証するものではないのです。この事実は、私たちが魚を選ぶ際の視点を、個人の健康だけでなく、地球全体の持続可能性へと広げることを求めています。
養殖魚に関する懸念点とその技術的進展
次に、多くの人が懸念を抱く養殖魚について考察します。一般的に指摘される養殖魚の懸念点とは、主に「抗生物質の使用」と「餌の品質」に関連するものです。これらの懸念は、過去の養殖業が抱えていた事実に根差していますが、技術の進歩と共にその様相は大きく変化しています。
過去の課題:過密飼育と抗生物質の問題
かつての養殖業では、狭い生け簀で魚を高密度に飼育することが一般的でした。このような環境では病気が発生しやすく、その対策として抗生物質が多用された経緯があります。これが「養殖魚は薬剤が多用されている」というイメージが形成された一因です。消費者の健康への影響や、薬剤耐性菌の出現といった問題が指摘されたのも事実です。
現代の課題:餌の品質と環境負荷
現代の養殖業においても、課題は存在します。その一つが、餌の問題です。多くの養殖魚の餌には、イワシなどの天然の小型魚を加工した魚粉が使われています。これは、養殖のために天然の水産資源を消費するという構造的な課題を内包しており、「Fish-in Fish-out ratio(FCR)」という指標でその効率が評価されています。
また、養殖場から排出される食べ残しの餌や排泄物が、周辺の海域を富栄養化させ、環境に負荷を与える可能性も指摘されています。
技術革新がもたらす持続可能な養殖
しかし、こうした養殖魚に関する懸念や環境負荷といった課題に対し、養殖業界では技術革新が進められています。
抗生物質の使用については、ワクチンの開発や飼育環境の改善により、その使用量を大幅に削減する動きが世界的な潮流となっています。国によっては、厳しい基準のもとで使用が管理され、出荷前には休薬期間が設けられるなど、安全性を確保するための制度が整備されています。
餌に関しても、魚粉への依存度を減らすため、大豆などの植物性タンパク質や藻類などを活用した代替飼料の開発が活発です。これにより、天然資源への負荷を低減する試みが進んでいます。
さらに、排水を浄化して再利用する「陸上養殖システム」や、より沖合の潮流が速い場所で養殖を行う「沖合養殖」など、環境負荷を最小限に抑える新しい養殖技術も実用化されつつあります。養殖業は、かつてのイメージから変化し、持続可能なタンパク質供給源としての役割を担うべく、変化を続けています。
ポートフォリオ思考に基づく合理的な魚の選択基準
ここまで見てきたように、「天然」と「養殖」は、それぞれにメリットとリスクを抱えています。どちらか一方が絶対的に優れているというわけではなく、私たちはより解像度の高い視点で、個々の製品を評価する必要があります。これは、金融資産を評価する際に、株式や債券といったカテゴリーだけでなく、個別の銘柄の事業内容や財務状況を精査する「ポートフォリオ思考」と共通する考え方です。
では、具体的に私たちは何を基準に魚を選べば良いのでしょうか。
判断基準としての認証制度:ASC認証とMSC認証
複雑な生産背景を消費者がすべて把握するのは困難です。そこで有効な手段となるのが、第三者機関による「認証制度」です。
ASC認証(水産養殖管理協議会)は、「責任ある養殖」によって生産された水産物に対する国際的な認証制度です。環境への負荷を最小限に抑え、労働者の権利や地域社会にも配慮している養殖場のみがこの認証を取得できます。養殖魚を選ぶ際には、このASC認証のロゴが、持続可能な選択をするための客観的な指標の一つとなります。
一方、天然魚を選ぶ際にはMSC認証(海洋管理協議会)が参考になります。「海のエコラベル」とも呼ばれるこの認証は、水産資源と環境に配慮した持続可能な漁業で獲られた水産物であることを示します。
食物連鎖を意識する:小型魚という選択肢
健康リスクと環境負荷の両方を低減する合理的な選択肢として、食物連鎖の下位にいる魚、つまり小型の魚を選ぶという方法があります。イワシ、サバ、アジといった魚は、生物濃縮による重金属のリスクが比較的低いだけでなく、多くの場合、資源量が豊富です。
また、これらの魚はEPAやDHAといった良質な脂質を豊富に含んでおり、私たちの健康資産に対しても優れたリターンをもたらす、合理的な投資対象と考えることができます。
産地と情報を確認する習慣
最終的には、私たち消費者が生産背景に関する情報を得ようとすることが重要になります。その魚がどこで、どのように獲られたのか、あるいは育てられたのか。スーパーマーケットの表示を注意深く見たり、時には販売員に尋ねてみたりすることも有効です。生産者や流通業者が、トレーサビリティ(生産履歴の追跡可能性)の確保に努めている製品を選ぶことは、安全で持続可能な食のシステム全体を支持することにつながります。
まとめ
「天然魚か、養殖魚か」という問いは、もはや私たちの選択における本質的な分岐点ではないのかもしれません。天然魚であっても海洋汚染や資源枯渇の問題と無関係ではなく、養殖魚もまた技術革新によってその課題を克服しつつあります。
私たちが本当に問うべきは、「その魚は、私たちの健康と地球環境に対して、持続可能な方法で生産されているか」という点にあります。その判断を下すために、ASCやMSCといった認証制度を活用し、食物連鎖を意識し、生産背景に関心を持つというリテラシーが、これからの時代を生きる私たちには求められます。
日々の食事における一つひとつの選択は、私たちの身体というポートフォリオを構築する小さな投資です。そしてそれは同時に、どのような未来の社会や環境を支持するのかを表明する意思表示でもあります。単純なイメージから脱却し、より構造的・多角的な視点を持つこと。それこそが、自分自身と未来の世代双方にとって、最も合理的な投資となるでしょう。



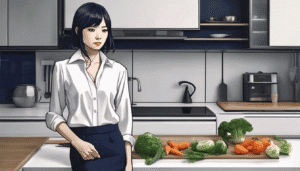
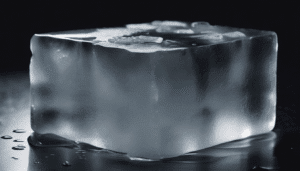

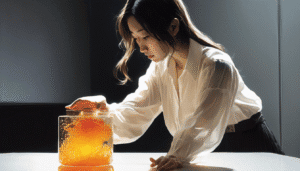

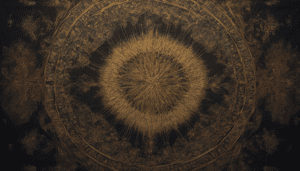


コメント